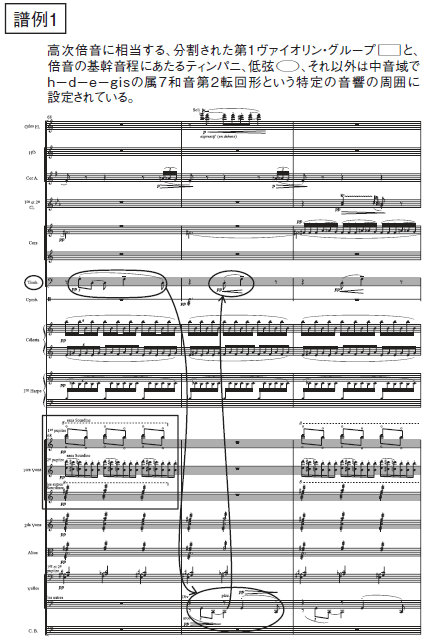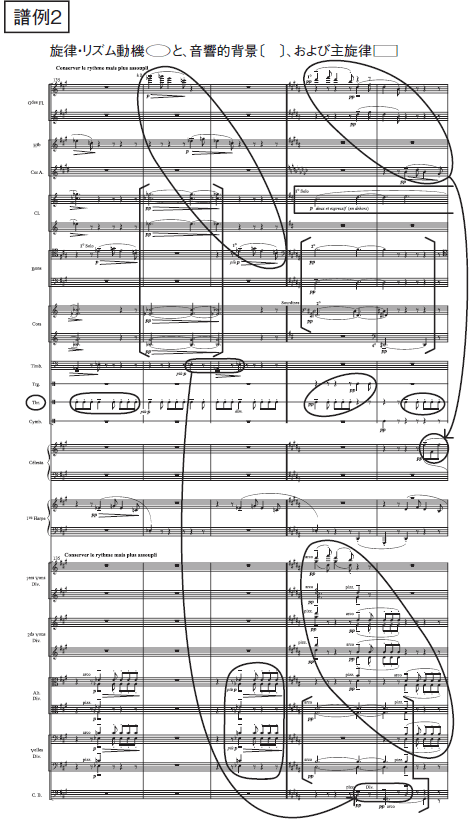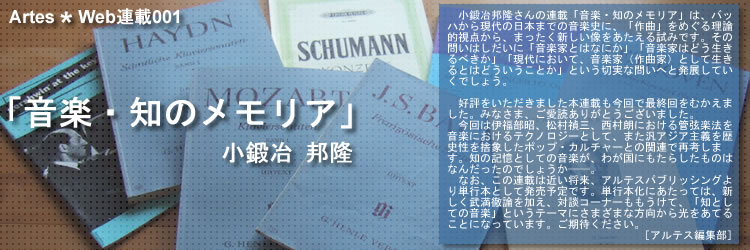
※本連載は、加筆増補のうえ、『作曲の思想──音楽・知のメモリア』として
単行本化されました。
ヨハン・セバスティアン・バッハの《インヴェンション》と《シンフォニア》は、今日にいたるまでピアノ学習者の必須の教材として知られている。たしかにバッハ自身、この2つの曲集を1723年にまとめるにあたり、序文によく知られた教育意図──1)2声および3声のたくみな演奏技術、2)カンタービレの奏法の修得、3)作曲の予備知識を得ること──を明記したうえで、冒頭に「正しい指導(Aufrichtige Anleitung)」としるした。
演奏技術、芸術的趣味、作曲法といった音楽家に必要な職能を体系的に指導することは、バロック、古典派の作曲家にとって、創作活動と同等の重要性をもっていたと考えられる。そうした伝統において、教育活動に比較的距離をおいていたその後のモーツァルトやベートーヴェンが、より近代的(19世紀的)な音楽家として評価されている事実は興味ぶかく思える。
芸術作品? 教材?
ところでバロック、古典派期の専門教育(職業教育)における学習教材の目的は、演奏、作曲両面における伝統的技法と当世ふう趣味の修得と考えてよいだろう。バッハの《インヴェンション》と《シンフォニア》の各15曲は、多様な作曲技法と演奏技法修得への導入が意図されている。ルネサンス以来の伝統的対位法にくわえて当世ふうの和声的様式(通奏低音)という時代の共有財産を基準に、時代の要求する演奏・表現技法をモデル(範例)として学習できる作品集として構想されているのである。バッハにおいては、作曲家の創作が個人的価値をもつのは当然としても、さらに共有されるべき知識(savoir)としての継承=教育を意図する水準が、作品そのものに設定されていると考えてみる必要があるかもしれない。
秩序の再構築としての配列
分析・演繹可能な秩序の内部に特定の意味性を発見することは、バロック的世界観といえるが、そのひとつの過程を、バッハの作品集の配列にみることができる。その過程をここでみてみよう。
《インヴェンション》《シンフォニア》は、1720年以降の初期稿において、それぞれ《プレアンブルム》(前奏曲)、《ファンタジア》(広義の対位法的楽曲)とされ、長男フリーデマンの教育用作品集《ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハのためのクラヴィーア小曲集》に、異なった順序でおかれていた。ここでは《インヴェンション》についてみてみよう。
音階的にハ音からロ音にいたるまで上行する、白鍵で主和音が作れる7つの調(ロ短調のみ伝統的に一部半音的変化をうける)と、変ロ音からハ音まで下降する、前記以外の臨時記号をともなう主和音による8つの調による配列が《プレアンブルム》にみられる(「曲順と調の比較表」参照)。
全体的には4つの嬰記号、4つの変記号内の長短調のうちから、長調では音響的純度を最低限保てる4つの嬰記号、3つの変記号を網羅した調律法(ミーントーン)を前提に構成されていると考えられる(《平均律クラヴィーア曲集》にいたる調律=音律の問題については今後の連載でふれる)。
バッハは《ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハのためのクラヴィーア小曲集》から《インヴェンション》に再編成するにあたり、いくつかの重要な改訂をおこなっているが、各曲の音楽的水準には大きな変更はあたえてはいない。しかしながら個々の作品の配列を変化させることで、新たな秩序の発見、あるいは再組織化を継続する機能をあたえたとも考えられる。
新たな配列・配置=装置
バッハは《インヴェンション》で、同主調どうしのまとまり(ハ長調、ハ短調など)を前提に、ハ音からロ音にいたる上行のみの再配列をおこなった。とうぜん変ホ長調のように、対になる(6つの変記号が必要な)変ホ短調をもともと欠く場合も生じる。
しかしながら、この対になる音階音6音(ハ、二、ホ、へ、ト、イというヘクサコルド[伝統的ソルミゼーション])から生ずる計12の同主調と、それ以外の、組み合わせをもたない残り3つの調(変ホ、変ロ、ロ)を上行順に挿入する配列があらためて作り出される(「曲順と調の比較表」参照)。
この結果、同主調どうしの各曲の対応、また同主調の関係をもたない独立した3曲の特性、および両者のグループとしての関係が、結果的に《インヴェンション》における新たな順序も含めて複雑化する。15曲各曲が原則同一なのに対して、全体としての配列(Disposition)の変化から生まれる配置=装置(Dispositif)とは、なんであろうか。
対比をつうじて世界へ
《インヴェンション》第1曲と第2曲を比較してみよう。がんらい冒頭におかれていた第1曲にたいして、第2曲は初期稿では第15曲(終曲)であった。技法的にも第1曲の単純模倣に対し、第2曲の継続模倣(カノン)というように、前者の不断の創意(インヴェンツィオ)による自発的な発展に対し、後者のカノンによる2小節の先行楽句から対声部の模倣という後続楽句を創出する、自律的組織化による楽曲構成が対応する。とうぜんながらバッハの当初(初期稿)の学習プランとしては、音階的上行・下行という調的プランをつうじての、この発展的な対比が目的であったと思われる。しかしながら他の同主調どうしの組み合わせの基本原理にもみられるように、《インヴェンション》では(上行のみの調的プランとして)直線化されたにみえる構想も、そのコンテクストにおいて並列化することで、相互に入り組む螺旋的対構造に変化したともいえよう。
たとえば初期稿ほんらいのハ長調、ハ短調の始点と終点の回帰的関係が対比的=相補的に組み合わされることで、究極的な回路(音楽用語でいう連作[Zyklus])が設定され、15曲それぞれの構造(形式)を超越し、配列そのものが形式を生み出すべく起動する「ネットワーク」という世界認識の原理=装置が試みられるのである。こうした原理はバッハ後期の連作《フーガの技法》において、極限的に追究されるものといえよう。
さらに若干の例をあげるなら、《インヴェンション》第3、4曲(二長調、二短調)でコンチェルトと舞曲というバロック的器楽書法の対比、第6、7曲(ホ長調、ホ短調)における伝統的対位法的書法と当世ふうギャラント(和声的)様式、第10、11曲(ト長調、ト短調)における前奏ふう(即興的)技法と修辞的(衒学的)な技法の対比というふうに、初期稿から再配列されることで顕在化した新たな学習意図が指摘できよう。
《インヴェンション》では音楽的意味のみならず、内包する学習内容のプログラミングの変換の可能性においても、「作品」という水準が設定されるのである。
音楽という知、あるいは歴史的記憶(メモリア)としての音楽
音楽とは世界認識であるといった議論に、とりわけ郷愁をおぼえる必要はない。けっきょく音楽という行為じたいが、人間精神における知のあり方を代償的に再構成するともいえるのだから。
継承され不断に再構築される音楽は、つねに制度化されたあり方ともいえる。なぜなら音楽家の基盤はつねに社会的・文化的制度と不可分に位置づけられ、その変動は失われたものを伝統、変化したものを革新と称しつつ維持されるところからも推測できよう。
音楽における創作原理=作曲技法は、その表現原理である演奏技術とともに、巨大な歴史的記憶を構成する。その記憶=歴史(メモリア)は、伝承による音楽的ネットワークの修復と拡大を、制度として音楽家に要求しつづける。たとえそれらが、ヨーロッパ近代という局地的、時限的な制約をそなえていようと、人間精神の普遍的な原理を、特化された時代的パラダイム(範例)から、逆説的に明らかにするのである。
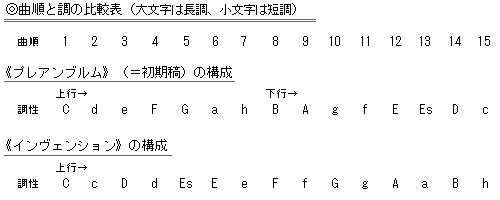
ヨハン・セバスティアン・バッハの《インヴェンション》と《シンフォニア》に想定されるところの、教育的・理論的水準についてはすでにふれた。1723年にまとめられた、この2つの曲集から、およそ20年後には《フーガの技法》というタイトルで知られる、バッハの対位法技術の秘儀的作品集が構想されたと考えられる。
《フーガの技法》の作曲は1742年以降、死の前年である1749年にいたるまで、断続的に進展したと思われる。《フーガの技法》は単一主題によるフーガとカノンによる連作(ツィクルス)として、未完に終わったとしても、《インヴェンション》と《シンフォニア》において体系化が試みられた対位法にかんする、極限的な理論的作品であることにまちがいない。
外部から内部へ
前回、《インヴェンション》の配列・配置という装置(Dispositif)を通じて、そこに理論と学習のプログラムを読み取った。《フーガの技法》は未完の作品として、従来から、自筆譜とバッハ自身による出版の意図をめぐる、さまざまな水準での配列が問題とされているが、具体的にバッハ晩年の理論的構想を推測してみよう。
外的な構造的枠組みとしては、1)コントラプンクトゥス1-4=基本主題と反行主題による4声単純フーガ、2)コントラプンクトゥス5-7=基本・反行主題による4声フーガ(Gegenfuge)、3)コントラプンクトゥス8-11=3声と4声の三重フーガに囲まれた、12度と10度音程による4声転回フーガ、4)コントラプンクトゥス12-13=4声と3声の鏡像フーガ(反行・基本)、5)4曲のさまざまな2声カノン、6)没後出版された楽譜には、さらにコントラプンクトゥス13の2台のクラヴィーア用編曲とコントラプンクトゥス10の初期稿、未完の4声フーガとコラールBWV668が収録されている。
1)~5)がほんらいの《フーガの技法》の構想にかかわる対位法的範例であると考えられるが、6)の未完フーガは、基本主題と四重フーガを実現する可能性において、この作品集ほんらいの構想にふくまれるのではないかと考えられてきた。
こうした外部の配置の重要性はとりあえずおくとして、ここではコントラプンクトゥス8と11のふたつの三重フーガの内部構造から、《フーガの技法》の理論的水準を読み解くコード(体系としての規範)をみてみよう。
多重フーガと転回対位法
コントラプンクトゥス8と11は、それぞれ3声と4声の(3つの主題による)三重フーガの範例として、第3グループの外枠として置かれていると考えられる。内部に置かれたコントラプンクトゥス9と10は、基本主題にたいし、それぞれ12度と10度による対主題の転回対位法を可能とする二重フーガである。
伝統的対位法の重要な技法である転回対位法は、対応する主題間で声部位置を上下に転回するさい、相互に対応する音程が変更され、音響的テクスチュアが変化するきわめて高度な技術である。とうぜんながら《インヴェンション》や《シンフォニア》では、基本的な音程である8度の転回音程のみが用いられているが、こうした転回対位法の歴史的意味については、次回でふれる。
第3グループの範例(歴史的パラダイム)としての意味は、外枠である8度音程の転回による三重フーガと、内部の12、10度音程による二重フーガの交差から生みだされる。音程の転回原理(8、12、10度)にもとづく主題の多重化による、新たな音楽的テクスチュアのオートマティックな生成の原理が(局部的とはいえ)試みられるといえよう。さらにコントラプンクトゥス8と11の三重フーガの構造は、きわめてまれな事例であるが、互いの主題性と構造において浸潤しあう特異な関係を前提としている。それぞれの構成をみてみよう(「構成比較表」参照)。
内包・連鎖・外延
多重フーガとして、それぞれの構成を組み立てているのは、個別の主題(と他主題との結合)による複数のフーガ提示である。5つのフーガ提示中、フーガ3を中軸として、前後の2つのフーガを配置する構成は共通している。しかしコントラプンクトゥス8では、あきらかにフーガ2とフーガ4が、主題性においてシンメトリーをなし、形式が「内包」により生じているといえる。コントラプンクトゥス11では、フーガ3を中軸としつつも、フーガ1と3、フーガ2と4、フーガ3と5という、互いに交差しつつも「連鎖」し(先行部分を集積しながら)「外延」化する形式が派生している(「構成比較表」参照)。
2つのコントラプンクトゥスで用いられる基本主題と2つの主題は、コントラプンクトゥス11においてさらに新しい主題が加わる(交換される)ほかは共通しているので、それぞれのフーガ提示は(場合により主題基本形・反行形を入れ替えたとしても)構造的にきわめて類似したものとなる。対称的なフーガ提示に対し、各エピソードはバッハのフーガにみられる同様の対称性よりも、各フーガ提示部と相互に入り組みながらも、むしろ経時的展開をおこなうが、ここではこの問題にはふれない。
ほぼ共有された音楽的テクストの構造化の方法的な差異のみが、この2つのコントラプンクトゥスを個別化している点に注目しよう。
内部から外部へ
16世紀後半のザルリーノの音楽理論以来の、伝統的対位法のモニュメンタルな作品集として構想されたと考えられる《フーガの技法》で、バッハは対位法による音楽的テクスト生成の方法を範例化することを意図したといえる。
《インヴェンション》と《シンフォニア》における、多様な様式による孤立した自発的な創作を、一定の配列・配置の許に新たな構造原理に集約していく方法に対して、《フーガの技法》では、アプリオリ(歴史的)な構造原理が各部分(コントラプンクトゥス)を規定していく方法が対峙する。
コントラプンクトゥス8に内在する構造が、その内部性をコントラプンクトゥス11と共有することで、内部が他の外部を内包しつつ外延化する原理が、音楽の生産性を保証するといえる。網状化して内部と外部を交換し増殖しつづける、その可逆的システムと不可逆の時間形式としての音楽的テクストは、やがて第4グループとしての、時間(同一の時間形式)と空間(音程的総反行と声部転回)の歪みとしての「鏡像フーガ」(コントラプンクトゥス12、13)の音楽的実存の極北にいたるのである。
時間という係数のもとにあらゆる現象を推移として解析する、近代の流儀に慣らされたゆえか、分類と記号化による凍てついた知の極限を、われわれは見失ってひさしい。バッハという、音楽における理論と学習のネットワークとしての知の記憶装置(メモリア)を、再起動させる刻(とき)がおとずれたのである。
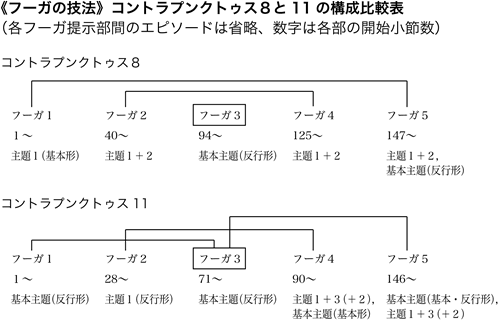
ヨハン・セバスティアン・バッハの《インヴェンション》《シンフォニア》と《フーガの技法》の音楽じたいに設定された、教育・理論的水準の一端を、前2回の連載でみた。
今回は《インヴェンション》《シンフォニア》がまとめられたと思われる1723年に先立ち、1722年ごろにはすでに成立していたと考えられる《平均律クラヴィーア曲集第1巻》から、よく知られているハ長調とハ短調の前奏曲とフーガを中心に、再度教育・理論的構想をみてみたい。同時に体系的な規範としてのコードが、読み解かれるべき暗号(信号)としても重要な意味を、テクストに内在させているところにも注目しよう。
隠された重複するテクスト
《平均律クラヴィーア曲集第1巻》の有名なハ長調の前奏曲は、《ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハのためのクラヴィーア小曲集》にみられる24小節の初期稿に各1小節計4カ所の部分的挿入と11小節の終結部分を追加するという規模の拡大のみならず、複雑なテクスト的再構成がおこなわれている。また初稿6小節以降は、右手3声、左手2声の和音配置のみ略記されている。とうぜんながら最初の5小節間で用いられているリュートふうの奏法(書法)にしたがって演奏できるのであるが、通奏低音法の実施例とも考えられるいっぽう、解読される体系(コード)を示しながら(初稿)、創造の段階的プロセス(改訂稿)を示唆するというバッハの教育・理論教育への基本姿勢がみられる。
ところで前者と調性的(同主短調)に対応する、鍵盤楽器特有のトッカータふうのハ短調の前奏曲(終結部分が初稿に対し11小節拡大された)は、おおむね右手3声、左手3声の和音の組み合わせが、ハ長調前奏曲同様に小節内で1~2つの和音を通奏低音の実施例として、音形化を要求される。さらに最初の9小節間はハ長調前奏曲(改訂稿)とほぼ同一の和声進行が用いられている。ハ長調前奏曲の9小節間には2カ所の新たな挿入(5、8小節)がおこなわれているだけに、結果的な音楽的テクストの重複の意味は大きい(譜例1参照)。
とうぜんながらバッハは、これらの対応する前奏曲に隠された重複するテクスト(同一の5~6声の和声進行)から、類型とそれらの差別化という課題を具体的に指示し、両者の異なる創作プロセスと演奏法のモデル(規範)を実施例として学習者に提示しているとも考えられよう。
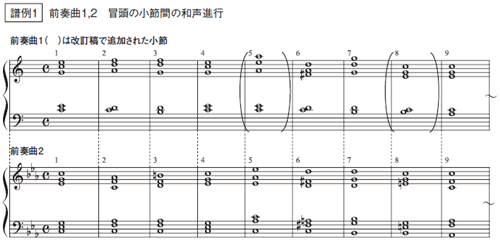
オシレーション(変動)・可変性(転回対位法)
前回にもふれたが、伝統的対位法の重要な技法である転回対位法は、対応する主題間(あるいは主題と対主題の間)で声部位置を上下に転回(交換)するさい、相互に対応する音程が変更され、音響的テクスチュアが変化する。《平均律》への導入過程と考えられる《インヴェンション》《シンフォニア》では、基本的な8度音程(1:2)の転回が用いられている。《平均律》の最初の2つのフーガでは、より複雑な12(=5)度音程(2:3)の転回が、〈フーガ1〉ハ長調の主題?対主題(2~3小節と6~7小節)で断片的に、〈フーガ2〉ハ短調の対応するエピソード間(5~6小節と17~18小節)でより厳密に用いられる(譜例2参照)。さらには〈フーガ4〉嬰ハ短調の終結部(107~108小節)では10(=3)度音程(4:5)が、伝統的な同時転回の技法(カノン・シネ・パウシス=先行・後続声部が同時に導入される、模倣間隔のないカノン)で導入されると考えられる。より高度な対位法技法の修得が《平均律》の課題の一部であることはまちがいない。
転回音程の変更は2つの声部(主題)間で交わされる、あたかも信号の変換のように、音程=振動数の変動により、音楽的素材の無限の多様化による消耗を回避しつつ、限定された素材の構造を可変的に多様化する方法を試みるのである。
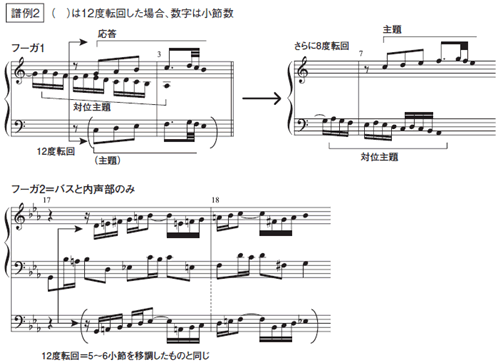
暗号数(コード)=14
よく知られているようにバッハは、自身の名前のアルファベットの数字への置き換え(BACH=2+1+3+8=14)による数14を、主題の音符数や、小節数、楽曲数に用いている。あきらかに意図的と考えられる例はそれほど多くはないが、〈フーガ1〉の主題の音符数は14であり、これは〈インヴェンション1〉の最初の主題の音符数を14にするための変奏を、自筆譜にわざわざ書き加えたことからも推測されるように、モニュメンタルな曲集を開始するにあたっての――b-a-c-hの音名によるものと同様――自身の署名であり、解読されるべき暗号(Sign=Code)でもある。
また〈フーガ1〉は、前半最後と後半最初の小節が共有(第14小節)されていることを前提に、それぞれ14小節からなっている。また〈フーガ2〉でも終結部分3小節以外、前半・後半14小節から構成されている。とうぜんながら小節数の一致のみならず、構造的に2部分性が主調・属調の対称性において成立するため、《インヴェンション》《シンフォニア》にみられる多部分性(おもに主調・下属調の対称性を枠組みに他の近親調を配する形式で、バッハのフーガ形式の一般的な特徴でもある)とはあきらかに異なるマニエラ(様式・仕様)がみられる。
主調・属調部分が相互に折り合わされた形式は、バロック組曲の舞曲形式や、のちのソナタ形式の初期の形態にしばしばみられるものであるが、バッハが《平均律第1巻》のフーガでしばしばそれらを用いているのは、バッハ自身の1720年前後の様式的な問題として理解できることなのであろうか。
音律と調律・TemperamentとTuning
《平均律》でバッハが用いた音律と調律法についてはさまざまな議論がある。
当時から知られていた5度圏循環の調領域によらず、ハ長調から同主調を組み合わせて半音階的にオクターヴを上行する方法は、《インヴェンション》と《シンフォニア》が全音階的に音階を上行する方法と対応する。
しかしながら、当時一般的であった純正3度を特徴とする中全音(ミーントーン)や、純正3度か純正5度を組み合わせたヴェルクマイスターなどによる調律法を前提に考えれば、同主調どうしの組み合わせでは、純正5、3度を5度圏に配分するさいの(シャープ系、フラット系の調の)相補性から、音律的な差異による音響的な特性化が生じやすいといえよう。
また用いられる調の内においても、音律・調律のひずみは、たとえば《平均律第1巻》の5声の〈フーガ4〉嬰ハ短調の主題におけるhis-eや、応答主題のfisis-hの減4度が、嬰ハ短調(あるいは応答主題の嬰ト短調)という音階音相互の不均衡な配列に対して、つねに純正(あるいは純正に近い)3度音c-e、g-hという異名同音として響くことで、ますます音響的な異質性を強調することから、音楽的テクスチュアが形成される。従来、象徴的に論じられてきた減4度の特性は、具体的な音律・調律的特徴から考察する必要がある。このように不安定な音響的条件のなかで主題は特化され、さらに主題を通じてテクスチュアとしての構造化が進行し、きわどい平衡状態が調的変化における時間的経緯として生み出されるといえよう。こうした聴覚と演奏する手・指という身体的にしか感知できない条件と、そこから時間の彼方に構造を予見する音楽的知の冒険は、すでに失われて久しいのである。
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトが、スヴィーテン男爵をつうじてヨハン・セバスティアン・バッハの音楽を知ったのは1782年という。ウィーン時代の創作には、たしかにバッハふう──というよりも、バロック様式の反映がみられる。 教会様式やオペラ・セリアなどにみられる伝統的な擬古的様式(バロック的対位法様式)が、交響曲に代表される器楽様式に直接的に影響を与えるという現象は、なにもモーツァルトにかぎったことではない。しかし前時代の通奏低音技法に支援され、韻律的に調整された歌唱的旋律書法を基本とする、18世紀後半に典型的なモーツァルトの音楽語法=古典派様式に与えた影響は、むしろ異なる様式を相対的にみる視点にこそ本質的な問題が含まれている。
内面性の反映としての創作
ウィーン時代後期の代表作、交響曲第39番から第41番の3曲が、1788年の6月から8月にかけて集中して成立しているのは周知の事実である。これらの作品には豊かな旋律性と同時に、対位法的な主題(動機)展開の技法にささえられた、大規模な調的統一による音楽形式(ソナタ形式など)が、多様な管弦楽的様式により、それぞれの特性をそなえながらも高い水準で実現している。
なかでも交響曲第40番ト短調K.550は、他2曲にくらべて、編成においてのみならず、音楽においてもより室内楽的な内面的で精緻な表現をめざしているといえよう(とうぜんながら同名調によるハイドンの交響曲第39番〔1768〕からモーツァルト自身の交響曲第25番K183〔1773〕にいたる先駆的様式がある)。
ここにみられる修辞的にも複雑な旋律法は、モーツァルト特有の半音階法に彩られた、近代的人間性の陰影の微細な推移を表現する和声法と結びつくことから、後世の創作モデルとなるような新たな表現領域を開拓したといえよう。そこでは作曲家自身の内面が、創作行為にリアルタイムで、過敏にまた過激に反映する作曲法として問題化されるのである。作曲行為は作曲家個人における、内面的な危機=発作(クライシス〔crisis,crise〕)のシミュレーションともなる。
作曲家の内面性の反映としての創作という近代的原理は、バッハの創作にみられた世界の構築性としての音楽モデルといかなる関係、あるいは相違を生み出しているのであろうか。
形式という知の橋梁
ところで交響曲(単一楽章から多楽章にわたるシンフォニア)にみられるような、テクストに構成を準拠しない大規模な器楽曲の創作を保証するものは、各ジャンル固有の様式の問題というより、共有される形式の関与といえる。
大規模な調的統一による音楽形式とは、ソナタ形式にみられるような、主に複(多)主題の提示・再現における調的対応(主調と近親調間)と、主題的素材の調的展開(より広範囲の調的推移)から構成され、たんなる時系列による連鎖的構成と異なり、重層的なパラダイム(規範)としての創作の原理を設定する、まさに形式全体に理性的視点から照射される啓蒙(enlightenment)的な構造性ともいえるものが、時代の文化と呼応しつつ試みられたともいえる。
しかしながら、この制度的ネットワークは、各所に個人的事情による断絶と混乱が蓋然的に生じる可能性を残している。その理由については、今後の連載でより具体的にみていくつもりであるが、ここではモーツァルトのト短調交響曲から、いくつかの実例をさがしてみよう。
ふたたび音律と調律の問題
前回(第3回「セバスティアン・コード(3)」)、バッハの創作における音楽的実存としての音響現象と、身体性をつうじての音律・調律と創作・演奏の関係についてふれた。
モーツァルトの場合はどのような関係がみられるのであろうか。
1)第1楽章展開部は、提示部最終小節から4小節の木管アンサンブルの短い移行句(100~103小節)をへて、提示部冒頭の主調ト短調から半音低い嬰へ短調で第1主題が開始される。18世紀において一般的であったと思われる5度圏からなる調領域(5度圏表参照)を前提にすれば、相互の遠隔調としての関係はきわだっているといえる。しかしながらむしろ、きわめて優れた聴覚の持ち主であったと推測されるモーツァルトにおいては、これらの5度圏から生じる相互関係よりも、提示部冒頭の第1主題が半音低く再提示される事実のみが、作曲家の内面の異常な生理(空虚感)に結びつく。とうぜん一般的な聴衆に感知されない水準で、創作が進行するのである。
2)第4楽章展開部では、第1主題による模倣的展開(4声ストレッタ)により、ト短調から嬰ハ短調を往復する反復進行(ゼクエンツ)が、5度圏の対極をそれぞれ15小節(161~175小節)と11小節(191~201小節)で結ぶ。これら5度圏の急速な移動(〔c-〕g-d-a-e-h-Fis〔fis〕-cis。5度圏表参照)は、過密な対位法的反復進行モデルにおいて実現される、転調というより音響現象の異常な推移から、一種の錯乱ともいえる精神下のできごとを象徴するともいえる。
こうした音律・調律の5度圏による安定的回路を遮断する危機的発作は、モーツァルト自身の身体的な衝動ともいえるが、これらの経緯がやがて、以下のように構造化され、展開部という形式機能を形成する水準において、精神作用としての音楽という近代が始まるのである。
3)第1楽章展開部の嬰へ短調の主題再帰以降、二重転回対位法によるバロック的反復進行(115~132小節)が、長期的に安定した調的推移(e~d、C~B)を生み出すのに対し、展開部後半の保続部分ふう推移(134小節以降)は、一瞬だけニ短調と遠隔調である変ロ短調の、聴覚的な鋭い痛覚ともいえる異名同音ふう転調を経過する(139~140小節)。その後の属保続音上の再現部への推移(153小節~)・導入(164~165小節)は、後者が展開部冒頭同様の木管アンサンブルによる移行句により、主題再現冒頭が隠微された特殊な修辞的意味を付与されている。
4)第4楽章展開部の急速な5度圏移行に囲まれた中央部分の16小節(175~190小節)にわたる、主調ト短調の対極点(5度圏表中の点線参照)としての嬰ハ短調の鋭い音響的対比は、モーツァルトの鋭敏な聴覚にとっては、ほとんどノイズ的な外界との軋みとしての、精神の緊張を生み出すともいえよう。
バッハおいては、創作・演奏の拠点としての特定の調選択とその推移が、モーツァルトにおいては、あくまでも相対化、および移行を前提とした通過点の意味に変化している。モーツァルトの鋭敏な聴覚と、自身が保持していたと思われる5度圏の絶対音的基準からのずれが、創作においての危うい均衡を生みだす。
というのは、ここでいう音律はむしろ、不確定な音響現象としての本来性において認知されているともいえるが、18世紀全般の基準とも考えられる、中全音(ミーントーン)などの使用における(嬰・変記号3つていど以内の)主調範囲の限定手段としての、調律における自閉的な5度圏の構築は、調的構造の均等化=(絶対音高による)平均律への移行を必然化するのである。開かれた音響現象としての本来の音律の意味は、概念的なオクターヴの均等な分割による調律法=平均律という、音響学的な暴挙ともいえる制度(構造)の背後に、その闇をさらに深くする。
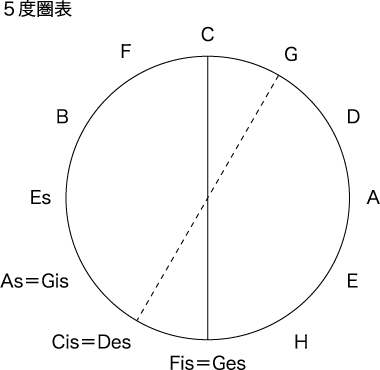
音像の錯乱
さらにモーツァルトの聴覚の特異性に注目しよう。
有名な第3楽章のメヌエットは、このジャンル(舞曲)としてはやはり異例な対位法的書法で貫徹される。しかしながらここでは、対位法という網状的管理技術よりも、本来の音響現象としての異質さに目を向けてみよう。
メヌエット主部前半は、主に両外声2声の対位法を中心として、控えめに内声部が充填されるていどの、異例のむき出し(déplouiller)の書法といえる(ハイドンの初期交響曲にも、通奏低音で補填されない両外声のみの書法、という前例がある)。小節構造上の韻律(メートリク)の3+3+4+4という(舞曲にあって例外的な)不規則性は、主部後半(15小節以降)の最初の9小節間(3+3+3)にもみられるが、その後は4小節構造に落ちつき、最後の結句(40~42小節)のみ、ふたたび3小節となる。
主部後半最初の9小節間はメヌエット主題による弦バス低声部(Vla、Vc、Cb)に対し木管上声部(Fl、Ob)、ヴァイオリン2部による対位上声部は木管低声部(Fag)で重複されるため、主要2声部は対声部について相互に超過現象(オーヴァーラップ)をひきおこすともいえよう。
このように本来の音響的な上下関係が、特殊な対位法的・楽器的書法で、意図的に混乱させられる状況がみられるのである。バス声部に転回したメヌエット主要主題に、上声部の対位声部を与えるという伝統的な対位法的書法において、モーツァルトの異例ともいえる聴覚の錯乱として、倍音的に上行する音響イヴェント(音律)が意図的に混乱させられるのである。
もし作曲家に近代的な意味で精神性というものがあるのであれば、これらは主体とは異なった水準で、精神現象の亀裂が実体化・構造化されたものともいえよう。音楽は知の基本モデルから特化して、近代的文化制度としての知の均質化を回避しながら、結果的に作曲家の主体性を解体しつつ、新たな暫定モデルをかぎりなく増殖させるのである。
「確かに、モオツァルトのかなしさは疾走する」(小林秀雄)のではなく「迷走するオブセッション(強迫観念)」。これらのランダムな拡散が、やがて平衡状態に達するときに、音楽はシステムとしての危機(クライシス)をむかえる。
ルードヴィッヒ・ファン・ベートーヴェン(1770-1827)が1803年に完成した交響曲第3番《エロイカ》では、従来からさまざまなかたちで言及されてきた音楽の革新的な意味のみならず、作曲という行為の新たな水準が設定されたといえる。
《エロイカ》における、その異例なまでに拡大された形式と、特異な音楽的個性は、あたかも近代的芸術の誕生と同一視されてきたといってもよいだろう。
しかしながらそこで用いられている技術は、音楽的テクストを生み出す基準(18世紀的伝統における規範性[モデル])としてよりも、すでにパラダイム(規範)と化した「交響曲」という複雑なテクストを統御する技術(近代的テクノロジー)へと接近しているように思える。
18世紀以前の古典主義(いわゆる旧体制[アンシャン・レジーム])という前近代的システムに対し、フランス革命からナポレオン以降、19世紀初頭に出現する近代的システムが対峙するのである。
形式と統治
《エロイカ》第1楽章の拡大されたソナタ形式は、構成各部分の拡大のたんなる加算的な結果というよりは、現前するその広大な音楽的領土をいかに統一・統治するかという方法・複合的なテクノロジーの運用と、そのメカニズムの探求が課題となるのである。
三和音に単純化・記号化された第1主題に対して、多様な注釈・修辞が第1主題部から移行部へと地続きの領域を形成する。歌謡的な第2主題(83小節以降)、また第1主題と関連する小結尾(132小節以降)も、こうした多様なテクスチュアの構造のさなかに、象徴的・記号的意味として差別化されるにすぎない。ベートーヴェンの音楽について、しばしば語られるところの、主題とその発展にみる有機的統一とは、こうしたコンテクストより生ずるテクスチュアとして、音楽的素材を分類・配置する作曲法と考えるべきかもしれない。
近代的人間の象徴としての《エロイカ》主題は、提示されるやいなや、意識として内面化する(7小節以降)。再度主題が確認され(15小節以降)、発展する過程を「主題的技法(Thematik)」と言い換えることは可能だが、やはり「主題」じたいを対象化する作曲技法こそが、問題とされるべきであろう。
いうなれば、作曲技法としての主体性は、主題の側にはない。むしろテクスチュアとしての構造のなかに定位し、意図的に性格化された「主題」が、あからさまにまで対象化され、個別化されることで、統治=形式のネットワークが生み出される。
視点の在りか
第1楽章展開部は、その複雑で長大な規模により、《エロイカ》の巨大な相貌を象徴している。しかしながら展開部中央で出現する哀歌風の新主題(288小節以降)は、ホ短調という、主調=変ホ長調の遠隔調であり、また再度出現するさい(326小節以降)には変ホ短調という同主短調により、長大な展開部の折り返し地点として設定される(展開部図式参照)。
この新主題は、再現部に続く、展開部に比する長大なコーダ(これもこの作品の革新性とされる)にふたたび現れる(585小節以降)ことで、形式を生み出す諸関連性(有機性)のもとに組み込まれるかにみえる。しかしながら、むしろこの新主題(この楽章の主要主題からの乖離の度合いが重要であろう)を視点として、広大な形式的分布としてのテクストに一定の視野が設定されているとはいえないだろうか。
もちろん、この楽章におけるソナタ形式の扱いについて、(古典派にみる)伝統的モデル性というよりも、断片的主題性から構造化されるプロセス的発展という意味で、その革新性を強調するなら、その一過程(あるいは一時的な逸脱[エピソード])として新主題を理解することもできる。
しかしながら、これらの作曲法は、いっけん際限のない拡大にみえながらも、そこに一定の「規律」を生み出す内在的システムがあるように思える。作曲の規範(モデル)を生み出す(保証する)創作というよりも、創意のモデルとしてさまざまな個性の背後に、創造のメカニズムは身を潜めるのである。そして形式を一望のもとに見渡す、従来の分節点=主題や各部分の配分と異なる視点が、(意識する、しないにかかわらず)設定される。
暴力装置としての音楽
展開部における新主題出現にいたる経緯をみてみよう(展開部図式参照)。
移行部の動機による展開は、模倣的発展=フガート(240小節以降)から、動機的リズムのみを残し、第1主題部(25小節以降)にみられる、ヘミオラ化(254小節以降、3拍子2小節分が、2拍子3小節に聴こえる)に至り、(280小節以降)長7和音(転回形)=ナポリの6和音の変形から属短9和音(基本形)という、当時においても異例の不協和音を連続して用い、極点としての遠隔調=ホ短調の新主題を導入している。これらの不協和音は、身体感覚的な苦痛のみならず、ほとんど恐怖に近い感情を、当時の聴衆に与えたものと思われる。ここでは音楽的技法としての不協和音の歴史的な機能が、すでに形式を成立させるところの内面化した「規律」に対応すべく、懲罰ともいえる、もはや技法とは乖離した管弦楽的音響性の暴力へと変貌する瞬間である。そしてその直後の新主題の出現は、形式に潜む主体性(客体化)のまなざしであり、広大な展開部が一望される契機となる。
提示部同様に、移行部動機と第1主題部のヘミオラ・リズムによるテクスチュアから、第1主題音形が差別化される構図は、提示部の基本的テクストの転写・注釈となり、提示・発展という時系列としての伝統的形式は、新主題の出現によるパノラマ的展望(まなざし)を基点に、ネットワーク状の配置(disposition)、あるいは装置(disipositif)へと変わる。
身体性の意味、ふたたび
ベートーヴェンの音楽は、ある意味(本人も言明するように)、道徳的・倫理的といえよう。しかしながらそれらの「規律(discipline)」は、内面化(構造化)された身体性としてのみ体験可能ともいえる。ベートーヴェン後期様式に特徴的と考えられる、主題性の内面化(潜在化)としての構造性は、様式的発展の結果というよりも、むしろ諸関係のネットワークとして創造を実体化する手段として、「近代性」という装置の内部に遍在するものであろう。
またこれらの「規律」を起動させるものとして、音楽における身体性=素材のリズム的性格の強調、堆積、予測不能な変化・破綻といった手段が不可欠のものとなる。
《エロイカ》第1楽章が、主要楽章にまれな、どちらかといえば舞踊的な3拍子であり、さらに同終楽章の主題と一部の変奏が、バレエ音楽《プロメテウスの創造物》(1800-01)から流用されたことは偶然ではない(同様に同主題は《コントルダンス》[1802]の第7曲にも用いられている)。
第2楽章〈葬送行進曲〉も、第3楽章〈スケルツォ〉の小節構造の単位(4~8小節)で組織化された波状的運動性同様に、「行進曲」という象徴性のみならず、小節単位では極端に遅延化された拍動と、ほとんど痙攣的に細分化された装飾的リズム(冒頭のコントラバス音形のみならず、随所に聴かれよう)によって、やはり身体的に感知されるものといえる。
しかしながら問題としては、これらがベートーヴェンに特徴的な作曲様式として分類されることではなく、それらがいかに内面化(ベートーヴェンの聖化のキーワードでもある)され、いわば構造の側から、聴き手をどのように順化するかという聴取の制度化と、こうした作曲行為の主体性の在りかが問われなければならない。
同様に、いまだこうした「近代的人間主義」という視座のもとで、今日、作曲する意味を、自身と時代に問うてみるのである。
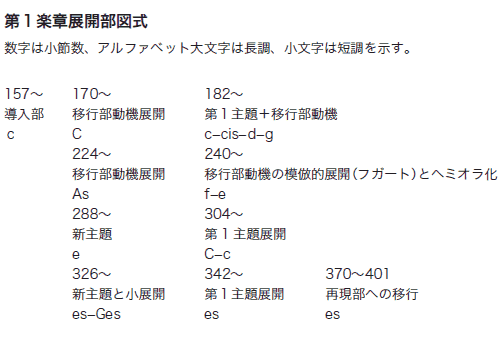
19世紀音楽におけるロマン主義には、孤独、憧憬、さすらいといった市民社会における現実逃避と夢想による代償作用が機能している。またロマン派とひとまとめに区分されるが、おのおのの作曲家の出自をみれば、いわゆる勤労者としての小市民(下層中産階級)から、あるていどの成功者(ブルジョワ=上層中産階級)としての市民社会の子弟が、その大半をしめることをあらためて指摘するまでもないであろう(これは今日にいたるまで変わらない)。
ところで孤独、憧憬、さすらいといった前出のロマン的概念は、音楽語法というきわめて個人的な表出を通じて表現(告白)されるのである。
ロマン主義的語法は、ブルーメも指摘するように、一般的に考えられているような革新性を根拠とするよりは、むしろ古典主義様式の延長としてのあり方こそが、重要であるといえる。とすれば、古典主義という汎用的な語法にあって、ロマン主義の個人化された表現は、内面の告白という特化された言説を形成するというところに注目したい。
《未完成交響曲》──シューベルトの場合
フランツ・ペーテル・シューベルト(1797~1828)のもっとも知られた作品である、《未完成交響曲》=交響曲第7(8)番ロ短調D759(1821)は、断章として2楽章のみ完成されたかたちで残され、その伝承と復活(1865年)は、まさにロマン的な物語を形成する。
断章という未完の、すべてが語られることのない物語は、ここでもきわめて個人的な告白のかたちをとっている。《未完成》の成立と関連して、しばしば引用される、同時期に書かれたシューベルトの自叙伝断片『私の夢』の内容は、別れ、さすらい、愛と苦しみ、あるいは死と至福のうちの浄化といった、第1、2楽章の音楽的特徴をあるていど象徴するともいえる。こうした聴き手の平均的理解の水準(ロマン主義という制度的言説)としての表現から、さらに具体的な音楽語法の実質をみてみよう。
調選択と楽器法という音響的特性化
18世紀にけっして用いられることのなかったロ短調、教会音楽ないしは劇音楽の楽器法に属するトロンボーン(もちろんベートーヴェンの交響曲に先例がある)、および特殊な調選択の結果、通常のティンパニの最高音域からさらに半音高いfis音をともなう、異常なほどに張りつめた管弦楽的音響性格による第1楽章は、ロマン的というよりも、ある種の劇的性格(悲劇性)を前提にしているといってよいだろう。
オーケストラ音楽の調性を決定するためには、(ドからラまでの音階による)ヘクサコルド読みが伝統的に用いられるが、さらに音域の高いシを主音とする場合、(それゆえ、オクターヴ低い「バッソ」がしばしば用いられる)変ロ長調のみが一般的に用いられてきた。ロ短調には、古典派の交響曲にみられる高音域の変ロ長調(たとえばモーツァルトの交響曲第33番など)と補完関係にある、低い変ロ長調(ベートーヴェンの交響曲第4番など)におけるオクターヴ低い「バッソ」を用いた落ち着いた調設定の伝統がなく、書式から排除されてきたのである。また、高い変ロ長調では、とうぜんトランペットとティンパニは、こうした高音域の調設定からは除外され、高音域のホルン(アルト・ホルン)が用いられてきた(トランペット、ティンパニのない、シューベルトの交響曲第5番変ロ長調D485では、通常のバッソのホルン[B管]を用いており、すでに伝統的なアルト・ホルンの用法はみられない)。
とりあえずはウィーン古典派の伝統的書法の枠内で、すでに6曲の交響曲を書いてきたシューベルトが、《未完成》に異例な作曲上の前提を設定することじたいが、作品の完成をさまたげたというような議論は不毛であろうし、むしろ《未完成》の表現を形成する音響的必然性を考察してみるべきと思える(第4回連載でとりあげた、モーツァルトのト短調交響曲の2本のホルンのうち1本は、アルト・ホルン[B管]であり、すでに調設定における、ある種の特異性を暗示している。ベートーヴェンにおいても、交響曲第7番が、ヘクサコルドにおけるイ長調という最高音域の特性=アルトとしてのみ存在するA管ホルンと、イ長調には通常用いられないトランペットとティンパニなどが、その躁状態ともいえる両端楽章の音楽的実質を形成する)。
また《未完成》にみるホルン(D管)の選択は慣習的、しかし同様にD管が選択されるはずのトランペット(E管)は、おそらく主調ロ短調にたいしてシューベルト特有のサブドミナント系の調・和音選択の傾向(展開部にみられるホ短調など)と関係があると思える。こうした古典的管弦楽法の延長線上に生じる(トロンボーンやティンパニの用法なども含めた)異質性において、《未完成》の表出性の特徴を、ほんらい考察すべきであろう。
主題の暗喩するもの
低弦のユニゾンで提示される導入主題(譜例1参照)は、ロマン派特有の主題においても歌謡的である点のみならず、むしろその構造の特異性においてきわだつ。たとえば4~5小節のa-fis-g-dという音型は、一般的な和声付けをすることの困難なもので、じっさい、展開部において(184小節以降)この音型による動機的展開にあたり、シューベルトは例外的な和声処理をおこなっている。とうぜんこの導入主題にひきつづき(9小節以降)、焦燥感と憧れに満ちた、本来の主要主題が提示されるが、展開部のみならず、楽章全体において用いられるのは導入主題のみである。
低音域で声をひそめ吟唱されるこの主題の意味は、とうぜんながら《未完成》の音楽的実質にかんするさまざまな言説を呼び起こす。しかしながらここでは、さきほど和声処理が困難と指摘した音型や、主題冒頭の3度内の動きから、単旋聖歌にみられるような旋法的性格が想定され、それらが《未完成》の劇的かつ(しばしば対位法的書法が援用される)宗教音楽様式と関連があるとは考えられないであろうか?
もちろん第2主題のレントラーふう(大衆的)性格が、並列的に配置されるが、62小節の唐突な全休止後の劇的な挿入部分(ここでもサブドミナント領域の変化和音が用いられる)が、つねに対比される。また展開部における劇的性格は、これらの身振りをより強調したものであろう。第2主題中間ペリオーデ(63小節以降)や展開部で表現されるものは、あきらかに精神的・身体的苦痛の物質化(音響的表現)であり、とうぜんその背後に演ずる主体の精神と、これらを実体化する苦痛に満ちた「告白」という制度的言説の存在が暗示される。
歴史的キリスト教社会と近代市民社会における、個人の在りかとしての「告白」という演技性が、表現する主体の根拠となるのである。しばしば言及されるところの、当時のシューベルトの性病の進行に由来する身体的苦痛と精神的不安が、どのように創作に影響をおよぼしたかという議論は、想像上の範囲を超えない。しかし自身と社会の関係としての倫理を顕在化するところの「病」は、おそらく「告白=悔悟」というキリスト教信者の統治としての密かな儀式性において、個人的=社会的に共有されるものとなる。この過程を抜きに、代償作用としての創作は、およそ困難なものになるであろう。
ペテロ(ペーテル)は悔悟する。
《悲愴》・チャイコフスキーの場合
ピョートル・イリイーチ・チャイコフスキー(1840~1893)が完成した最後の交響曲第6番《悲愴》(1893年初演)は、シューベルトの《未完成交響曲》(1821)と、ロ短調という、交響曲にあっては異例の調性を共有するのみならず、いわば本歌取りともいえる性格をもつものである。
その主題はあきらかに《未完成》第1楽章冒頭主題を暗示するとともに、おそらくは《悲愴(Pathétique)》というタイトルが示すように、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ《悲愴》作品13ハ短調の、冒頭序奏主題の引用とも考えられる(譜例1、2参照)。
《悲愴》交響曲にみる、ロマン主義における音楽表現としての「告白」の意味する問題を、シューベルトの《未完成》で考察した観点と関連させながら、再度検討してみよう。

ロマン派「交響曲」における宗教的イメージ
シューベルトの最後の交響曲第8(9)番ハ長調D944(1828)の、作曲家の死後11年をへた、メンデルスゾーンによる歴史的な初演(1839年、ライプチヒ)以降、その影響化にあるシューマンやブラームス(さらにブルックナーも加えられよう)の交響曲創作の歴史には、とりわけ3本のトロンボーンの使用(さらにチューバ1本も加わる場合もある)のみならず、ロマン主義の原点のひとつとしての「根源的な(ursprünglich)」もの、汎神論的な宗教的神秘性がみられるといってよいのではないだろうか。教会音楽様式に代表される、コラールふう主題や対位法による書法が、それらの拠点となる。
1877年に作曲された第4番以降のチャイコフスキーの後期交響曲では、ロシア固有の音楽的素材にくわえ、イタリアのベル・カント・オペラの旋律法とフランスのグランド=オペラからワーグナーにいたる管弦楽法によるオペラ様式、さらに、とりわけフランス・バレー音楽ふう趣味が、独自のロシア・西欧的な様式を生み出している点についてはいうまでもない。
ところで《悲愴》における宗教的イメージと考えられる箇所を検討してみよう。第1楽章展開部の激越な前半の頂点では、音楽的頂点(190小節)の変ロ音のために配されたともいえる変ロ管トランペットが、主調がロ短調であるにもかかわらず、第1楽章を通じて用いられている(上記「調選択と楽器法という音響的特性化」の項を参照)。その後、突如出現するロシア正教会の聖歌=死者のための賛歌(202小節以降)が、展開部後半の黙示録的ともいえる劇的頂点へと導く。聖歌の引用同様に、あたかも黙示録=終末論的な審判の時を告げる喇叭を暗示する、3本のトロンボーンとチューバによる斉奏(286小節以降)は、終楽章終結部直前(137小節以降)の、伝統的な埋葬時の奏楽(Equale)の様式を思わせる、やはりトロンボーンとチューバによる四重奏ともに、交響曲における宗教性の反映について考えさせられる。
音型的統一によるアフェクト
さらに《悲愴》では、第1楽章導入部最後の、全音階的な4度下降音型(15小節以降)のアフェクト(情緒性=冒頭6小節間の半音階的4度下降音型[e~h]の修辞的象徴性[悲しみ、苦痛など]ともかかわる)による、全4楽章における音型的統一ともいえる手法がみられる。
第1楽章全体において明らかなように、バレー音楽ふうイディオム(5拍子の異例なワルツ)にもとづく第2楽章や、焦燥的で諧謔的な(さらには暴力的でもある)行進曲としての第3楽章ですら、統一原理として作用している事実は興味深く思われる。さらに終楽章においても、アリオーソふうの悲痛な第1主題と、甘美な劇場ふう宗教様式のアリアを思わせる第2主題の構成は、明確な主題的統一によりながらも、たくみな和声法と管弦楽法により、みごとに差別化されている(譜例3参照)。
しかしながら、およそ主観的な傾向の勝った創作と考えられることの多い《悲愴》にあって、これらの(主題)音型的統一性の意味するものは、なんなのであろうか。
悔悟するペテロ
シューベルトの《未完成》で暗示されていた「告白=悔悟」の名のもと、宗教という名の劇場にあって、もうひとりのペテロ(ピョートル)の過激な演劇性が表出するものを、シューベルトの性病と同様に、同性愛嗜好というチャイコフスキーの精神的・生理的特質と、近代市民社会の倫理と対峙させるのは、たぶん、公平な議論とはいえないだろう。
創作という場における、(音楽的身振りを生み出す)書く主体の演技性とは、歴史的キリスト教社会の共同幻想に近いもの──《未完成》の宗教的悲劇性や《悲愴》の黙示録的情景──、あるいは聖なる音楽──《未完成》第2楽章の祝福された者〈ベネディクトゥス〉の鐘のイメージ(14~15、50_51小節など)──や、《悲愴》終楽章の第1主題の破滅的な最後の出現のさい鳴り響く、ホルンのゲシュトップ奏法による異常な(金属的)音色による弔いの鐘の幻想(126小節以降)──というかたちで実体化されるのであろう。これらのイメージを配置する内的規律こそが、(主題)音型的統一の意味であり、また創造する主体の意識のあり方でもある。やがて「告白」という内的体験の外在化は、ロマン主義的幻想の果てに、人間精神の識閾の病理的な領域として、「無意識」という音楽の新たなディスクール(精神分析)をも、編成するのである。
クロード・ドビュッシー(1862-1918)の音楽は、19世紀後半のロマン主義とフランス象徴主義の風土に開花し、いわゆる世紀末の芸術から20世紀初頭のベル・エポックの花咲く日々の思い出として、われわれの記憶に刻まれている。
さらに第一次世界大戦の前年、1913年に、ストラヴィンスキー《春の祭典》とともにロシア・バレエ団により初演された、オーケストラのための「舞踊詩」と題された《遊戯》や、戦時中の1915年に作曲されたピアノのための《12の練習曲》は、当初の否定的な評価にもかかわらず、第二次世界大戦後、シュトックハウゼンやブーレーズといった50年代の前衛作曲家たちによって、その新しい音楽思考の観点から再評価されたのは周知のことであろう。
ヨーロッパの旧世界を解体した2度の世界大戦をはさみ、その評価が相反する(異なる)とも考えられる、ドビュッシーの音楽を再考してみよう。
《選ばれた若者》
1902年の《ペレアスとメリザンド》初演により、ドビュッシーは作曲家としての社会的評価を確立させる。また私生活においても、銀行家夫人のエンマ・バルダックとの不倫、妻リリーの自殺未遂、そして離婚という世間的スキャンダルをへて、1905年にボワ・ドゥ・ブーローニュ街の高級住宅地に移り、エンマと同居を始め、一人娘(シュシュ)が誕生……と、彼が夢みた上流の生活と創作の日々を獲得する経緯は、評伝的事実にいささか収まりきらない意味をもつ。
貧しい勤労者の家庭であるドビュッシー一家は、クロード5歳のときに郊外からパリ市内に移り住む。ドビュッシーは歓楽街ピガールと下町のサン・ラザール駅界隈をなんどか移り住みながら、1872年以降12年間におよぶ、パリ音楽院での学習時代を過ごすのである。
苦労して手に入れた(3回の挑戦)ローマ大賞という、オペラ作曲家として約束された将来も、彼一流の反逆的ポーズに加え、生きるために上流社会の音楽サロンでパトロン漁りをしなければならなかった青年作曲家には、あまり役に立たなかったようだ。もっともワグネリズム一色のパリ音楽界にあって、ワーグナーにならって(après de Wagner)でなく、ワーグナーを超えた(après Wagner)オペラを夢みたドビュッシーは、パトロンのおかげの2度のバイロイト体験と、パリ音楽院で受けたオペラ的作曲法の徹底的な学習を下地にしつつ、象徴主義と世紀末ふうの雰囲気に満ちた《ペレアスとメリザンド》(1893-1902)を抒情劇として構想することで、あくまでも伝統的なグランド・オペラとの差別化をはかる。
虚無の工場
ドビュッシーは、エンマとの費用のかさむ生活を維持するため、次作オペラの構想を模索しつつ、管弦楽のための3つのエスキス《海》(1903-05)や、ピアノのための《映像第1集》(1905)以降の革新的な音楽語法を試みる。
ところで1906年以降、翌07年にいたる、創作上の不毛な時期が知られている。あたかも「虚無の工場(les usines du Néant)」(1906年4月18日の、ドビュッシーからデュランへの手紙)ともいえそうな沈滞感のなかで、創作は停滞する。
しかし革新的語法という新たな「投機」は、意外なところで試みられる。
豊穣なワグネリズムの記憶でもある、ドビュッシー初期の歌曲集《ボードレールの5つの詩》(1887-89)第3曲〈噴水〉の(ピアノ伴奏部分の)オーケストラ編曲は、あまり知られていない。ドビュッシーは、《海》や《映像第1集》で試みた、響きと時間(音色構造と形式)のより先鋭的な実験をここでおこなう。がんらいワーグナーに由来する、管弦楽編曲ふうピアニズムをもつこの歌曲のピアノ書法は、ここにおいて、さまざまな楽器の音色・音形(音高)・リズム(持続)・強度とアーテキュレーションによって、徹底的に解体されるのである。また複雑なフィギュア化による、音像の多様な変化・移動により、ほんらいの調性的支点が、より根源的なスペクトルに分解され、あたかも音響的な迷宮でもあるかの様相を示すのである。1907年2月24日にコンセール・コロンヌにより初演されたこの編曲は、否定的に評価されたのみならず、明らかにその場かぎりの機会的作品として無視されたのはとうぜんであろう(いまだ再評価されていない)。
そこにみる創作方法は、時代性を共有する、技術と様式による伝統的な制作術(musica poetica)としての作曲法に対して、20世紀全般の方向性として、個的で自律的な、「エクスペリメンタル(実験的=経験的)」な創造のあり方が対比される。
律動づけられた時間と色彩
1907年は、ふたたび創作の夏がおとずれる。
3曲からなる管弦楽のための《映像第3集》第3曲として知られる《春のロンド》の構想が確実に進展をみるのである。
「私はしだいに、音楽というものは、その本質からして、伝統的で厳格な形式のなかでくりひろげられるものではないと確信するにいたりました。音楽は律動づけられた時間と色彩なのです……」という、デュランにあてた1907年9月3日の手紙は《春のロンド》の進展を伝えると同時に、この作品の本質的に新しい意味を語っていると考えるべきであろう。
あまり議論の対象としてとりあげられたり、演奏されることも多いといえない、比較的短い作品《春のロンド》を具体的にみてみよう。
前出の手紙のなかでドビュッシーは、同作品における「非物質性」にもふれているが、おそらく特定の音色構造とその時間的持続が形成する音楽形式が、(力学的、機能的な)従来の調的和声にもとづく、伝統的形式による音楽展開と対比されていると思われる。以下音色構造と時間的持続の2点から《春のロンド》の図式を描いてみる。とりあえず伝統的といってよい、ロンド形式が浮かびあがる(図表参照)。
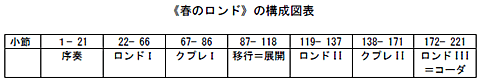
Images(映像)・現実と実存
管弦楽のための《映像第3集》(1905-12)は、《ジーグ》、《イベリア》、《春のロンド》の3曲からなり、ピアノのための《映像第1,2集》同様、各タイトルが暗示する描写的内容に反して、そこでは「現実(réalités)と異なるなにか」(ドビュッシー)、おそらく実存(réalité)が探求されている。images(映像=心象)を介して、現実界のとらえがたい変転そのものの背後に、本質的な現実=実存が眺望されるのである。
音響と時間の形式による新たな現実とは、現実の音響=ノイズと楽音、身体的リズムと音楽語法一般の韻律性の交わるところ、パルス(振動数)としての音高とリズム(音価)の相関性、そして調性的音響の倍音原理におけるスペクトルの試みとして探求される。
ところで身体的リズムとは、《映像第3集》のフォークロア的性格、《ジーグ》の英国、《イベリア》のスペイン(ハバネラなど)、《春のロンド》のフランス(《もう森へは行かない〔Nous n'iron pas au bois〕》と《眠れ、よい子〔Do,do,l'enfant do〕》といったフランス童謡が、5拍子の舞曲の主要主題として用いられる)の、特定のリズムパターンによる民謡ふう素材が、コンテクストを形成することを意味する。非ヨーロッパ文化圏への異国趣味とならんで、ヨーロッパ文化のファッション性は、今日の都市文化の原点としての国際都市、パリの同時代性(コンテンポラリー)の反映ともいえよう。
変ロ、変ホ、イ音という限定された音高を中心とする序奏(1-21小節)では、弦楽器のスル・ポンティチェッロ(駒の近くで)、スル・タスト(指板の近くで)という、通常の奏法に対して倍音の特徴的な制御と、字義どおり倍音を生成するハーモニックス奏法が集中的に用いられている。また同様にピッツィカートやトレモロも、音源アタック時の雑音やヴァイブレーションといった「変調(モデュレーション)」が問題となる。通常の楽音に対し、現実界の反映としての非楽音=ノイズが音楽的発想の原点となる。調的・和声的コンテクストに対し、音響的テクスチュアが対置され、新たな音楽構造・持続が試みられるのである。序奏部に現れる《眠れ、よい子》や、続いてロンドIにおける《もう森へは行かない》といった主題も、伝統的な主題性と異なり、たんなるテクスチュアの折り目に浮かびあがる音楽的瞬間を生み出すにすぎない。またほんらいのロンド主題と思われる第3の楽想(31小節以降)も、散在する一動機にすぎず、やがて音楽的展開のうちに散逸するのである(180小節以降)。
音楽的時間は、あたかも即興的な素材と形式のうちで、夢みるような持続として生み出される。
音響的スペクトルによる形式
1)クプレIの音響設定をみてみよう(68小節以降、譜例1参照)。
ここではスル・タストの弦楽器のトレモロとハーモニックス奏法により形成されるホ長調和音(実際には、イ長[短]調の属7和音e-gis-h-d)と、バスのオスティナート的なハ長調の複調的音響の摩擦が特徴化される。ティンパニの異例な高音をともなうg-cの張り詰めた音色感と、チェロのアルコ・ピッツィカートと分割された声部の形成する音色旋律としてのオスティナートの不変のバス進行が、調的推移とは異なる、音色的テクスチュアに聴覚を集中させる。そして高音域でソロ・グループとそれ以外に分割された第1ヴァイオリンや、他の弦楽器グループの生み出すトレモロやハーモニックスの、高次倍音に相当する動き(さらに木管楽器の微細な動機)が、細分化された振動数に相当し、中低音の倍音の基幹音程にあたる音程が、より緩やかな周期で反復されることで、音高(倍音)とリズム(音価)がパルス的に一致する、あたかも電子音楽的な発想がみられる。
シュトックハウゼンがドビュッシーの《遊戯》でおこなった分析は(『ウェーベルンからドビュッシーへ──統計的形式のためのノート〔1954〕)、とうぜんながら、50年代の具体音・電子音楽的発想を根拠とするものである。
2)さらにクプレIIへの移行とクプレII冒頭の音響設定を検討してみよう(135-139小節、譜例2参照)。
移行部(137小節まで)の中心的和音(音響)のas-c-es-gがクプレII(138小節以降)のgis-h-dis-fisと異名同音的変化により、音響的テクスチュアの変化が生ずる。単純な持続和音(長・短7和音)ではあっても、そこでは弦楽器群(補助的に木管楽器)の高音域から中音域への音像移動を、背後のハーモニックスを含む弦楽器と木管(ホルンを含む)の保続音響が、空間的に浮かび上がらせる。
また132小節以降、短く再現する第3の(主要)ロンド主題の最後の動機が用いられてはいても、(若き日のドビュッシーに強い印象を与えた)ガムラン音楽を思わすような、極小動機による一種のヘテロフォニーが意図されている、といってもよいかもしれない。
移行部におけるティンパニのリズムがコントラバスのピッツィカートに移り、いっぽうタンブラン(中太鼓)のリズムは不変であるところから、一定のリズムにともなう彩色法の変化が、律動づけられた音色としての局面を生成するのである。同様に、クラリネットに聴かれる、《もう森へは行かない》の拡大された旋律の彩色法でもある。
このように(2カ所のみの検証にすぎないが)各部分の固有の音色的テクスチュアが、コンテクストとしての形式を生み出す。《春のロンド》のみかけのロンド形式(類比による形成方法は《遊戯》と共通する)は、とうぜん伝統的形式としてではなく、音響的推移の形式としての音楽の対照、多様化という、聴覚上のフォーカス(焦点)を形成するにすぎない、といえばよいだろうか。
方法は異なるとはいえ、こうした管弦楽的音響にかんする新たな発想は、マーラー(第9交響曲第1楽章や《大地の歌》終楽章)を介して、1910年前後の新ウイーン楽派と共通項が認められる。シェーンベルク《管弦楽のための5つの小品》op.15第3曲〈色彩〉、ウェーベルンの《6つの管弦楽のための小品》op.6第4曲や、ベルクの《3つの管弦楽のための小品》op.6第1曲導入部などには、まさに楽音とノイズの音響的スペクトルがみられる。そして《春のロンド》の、1910年11月15日のニューヨーク初演をおこなったのが、マーラー自身であるのも象徴的といえようか。
同年3月2日に作曲者自身の指揮によりおこなわれた、パリ初演の後にみられる、用心深い批評に比べれば、「形式の崩壊」「痙攣的な」「混乱した響き」「常軌を逸したオーケストラの色彩」といったニューヨーク批評界の語調(H.-L.ド・ラ・グランジュによる引用)は、ドビュッシーの音楽というよりも、あたかもマーラーの後継者たちたる新ウイーン楽派の音楽を思わせる。
夢みるクロード
伝統的な音楽理解が、おおむね主題の提示・対比・発展・再現といった時間形式に支配されている事実は否定しようがない。しかしながら時間形式としての音楽を、聴き手はその時間を現実に所有することなしに、記憶と内的体験として、また時間的経過のプロセス(過程=手続き)全体として、把握するにすぎない。たとえば主題じたいがいかに正確に再現されようとも、一般的聴衆は、すでに提示された主題を正確に認知するのではなく、ありうべきプロセス=文化的慣習としてのみ、主題の再現を遡及的(形式的)に追認するのである。
近代における音楽の「形式」とは、その歴史的な根拠のあいまいさにもかかわらず、音楽聴取のテクノロジーの一部として、聴き手の音楽的理解の自由を「保障=担保(セキュリティ)」するものである。そして作者の名もこの「保障=保証」の一部となる。
しかしドビュッシーの音楽では、もろもろの音楽的契機(主題・リズム・響き・形式など)が、音楽的現実(実存)を生み出す瞬間を保証するのみといえる。時間=形式の彼方に、記憶と忘却、そして変容としての再生の刻を生み出す、作者の名も消失したところの自律的な記憶装置としての音楽的装置=配置(disipositif=disposition)が、ドビュッシーの夢みたものなのであろうか。
移ろいゆく魅惑の一刻を、永遠に留め置くためには、断続的に現前する音楽的瞬間を体験する快楽と、その喪失の空虚に堪えつづけなければならない。
モーリス・ラヴェル(1875-1937)は、しばしばドビュッシー(1862-1918)と同様、フランス象徴主義の作曲家として扱われる。しかしながら19世紀末から20世紀初頭のベル・エポックの風土を共有しながらも、彼はドビュッシーの死後(第一次世界大戦後)から、第二次世界大戦にいたる両大戦間のモダニズムを生きた作曲家でもある。
ビック・バンドを思わせる有名な《ボレロ》(1928)にかぎらず、それぞれ両手と左手のための2つのジャズふうのピアノ協奏曲(1929-31、1929-30)、ディズニー(アニメ)ふうのオペラ=ファンテジー・リリック《子供と魔法》(1920-25)などの作品に刻印された、1920年代という時代──絶え間なく生まれ消費される今日の国際的な都市文化の原型ともいえる時代──の祝祭の記憶をここに留めおくとしよう。
機械愛の時代
1905年、5度目のローマ大賞に失敗したラヴェルは、友人エドワール夫妻の豪華ヨットで河川をさかのぼり、ベルギー、オランダ、ドイツを訪れる。ベルギーとドイツの工業地帯はラヴェルをして「この精錬の砦について、この灼熱したカテドラル、ベルトの動きや汽笛や激しいハンマー音の素晴らしいシンフォニーに浸されているのを、どのように語ればよいのでしょうか。空は見渡すかぎり赤く、焼けるような深紅色でした……これらすべてが音楽的です! これをたぶん使おうと思っています」と書いている。
第一次世界大戦のおよぼした深刻な影響をとどめる《ラ・ヴァルス》(1919-20)でも、まさに操業中の工場の狂躁的なノイズであるかのような開始部分、分奏するコントラバスの凝集音(アグレガ)状の持続が、ヨーハン・シュトラウスふうの享楽的なウィンナ・ワルツへと変容し、ベル・エポックの終焉を思わせる自滅的なエロスとタナトスの戯れを繰りひろげる。
ラヴェルの音楽が、パリ国立音楽院で修得された伝統的(アカデミック)な音楽技法にもとづくものであるとしても、それらは特化した技術的観点(テクノロジー)から演繹される。ラヴェルの音楽の代名詞であるかのようにいわれる卓越した管弦楽法も、ほんらいベルリオーズ『管弦楽概論』(1844初版)にみられる科学的な分類・整理による楽器の扱い(概論)から、さらに各楽器の特定の技術的視点から可能な音楽表現を「技法(テクニック)」の名のもとに詳述した、ヴィドールの『現代管弦楽の技法』の出版(1904)に、多くを負っていることからも明らかであろう。
複製可能なテクノロジーが創造の契機になる以上、そこには消費されるモードとしての記号性が必須のもととなる。ワルツ(ヴァルス)という時代遅れゆえのキッチュなモード性が、特定の拍子(3拍子)の変形──3拍子ゆえの、いっぽうの足の拍の重複としてのアクセントの移動(ダンスのファッション性)や、両足交互の動きによる旋回(ターン)としての2拍子の混交(ヘミオラ)、定期的な終止形(和声的カデンツ)の配置による並置的な形式(ステップ・パターンの組み合わせ)──に置き換えられる。ダンスほんらいの身体性(リズム)とパフォーマンスとしての音楽構造(旋律・和声)が、創作原理となるのである。さらにこうした方法が、今日のポピュラー音楽一般の創作原理でもあることは、いうまでもない。
実験・治癒としての創作
ラヴェルにとって、逆説的ではあるが、管弦楽法とはかならずしもオーケストラ的な可能性を前提に実施されるものでのない。
前述したヴィドールの著作は、5度にわたるローマ大賞の試みにみられるような平凡な管弦楽法(ほとんどの評伝では、保守的なローマ大賞獲得のための、ラヴェルの偽装を想定しているが、保存されている課題作品全体からみるかぎり、当時の彼のもっていた管弦楽法の知識はかなり限定的なものといえる)から、画期的なピアノ曲集《鏡》(1904-05)の第3曲〈洋上の小舟〉の管弦楽化(1906初演、1950出版)にみられるような、大胆で実験的な試み(ラヴェル自身は試みと考えたゆえに、同作品は生前出版されなかった)への進展に、重要な役割をはたしたといえよう。《水の戯れ》(1901)以来の、リストふうの多様なアルペジオの合成から生じるピアニスティックな音響性に満ちた〈洋上の小舟〉は、もっとも管弦楽化が困難なテクスチュアといえるが、ラヴェルにとり、それらはむしろオーケストラのメカニズムの新たな探究にとって好適な素材となったといえる。ラヴェルは、原曲のピアノ的音形の最小限の変形のみで、同曲の音響的テクスチュアから、管弦楽書法としての再構造化を試みるのである。ここでは、まさに汎用的なテクノロジーとしての管弦楽法の修得が問題なのである。そしてそれらはまた、オーケストラ音楽という伝統的ジャンルを規定してきた表現と技法の関係を、一時的に切断したうえで、ヴィドールの著作のタイトルでもある、「現代管弦楽の技法」という高度なテクノロジーが可能とする音楽の在り方として、ここで新たに探求されるともいえよう。
管弦楽法がたんなる技法的役割を超え、創造行為の母体(マトリックス)として、実験的な工房となると同時に、不眠症のラヴェルを狂喜させたというヴィーネの表現主義的映画『カリガリ博士の診察室』(1919)同様、実験室=診療室(キャビネット)としての、今日における創造行為にみる、きわどく奇怪な時代精神の自己治癒的行為の基点、としての意味をももつにいたるのである。
反アカデミズムの神話、あるいは音楽のテクニクスとポリテクスによるエピソード
5度にわたるローマ大賞の試み(1900-03、1905)の挫折は、ラヴェルの革新的な音楽語法にたいする、パリ音楽院のアカデミズムの無理解と排除が原因とされてきた。
新進オペラ作曲家の登竜門としてのローマ大賞は、同時にパリ音楽院における和声法、対位法、フーガ、管弦楽法といった技術教育(エクリチュール)の目的をも明らかにしている。
ドビュッシーが3度目の挑戦で獲得し、ラヴェル後にはメシアンが2度の失敗で断念したローマ大賞は、19世紀におけるパリ音楽院の教育行政(ポリテクス)の要であり、同時に消費としての音楽=オペラ制作にかかわる技術的規範(テクニクス)でもあった。
14歳から30歳までの長期間(2年間ほどの中断がある)にわたってはいても、パリ音楽院在学中に、なんらの賞も獲得することが出来なかったラヴェルではあるが、とうぜんながらこうしたコード(規範)としてのローマ大賞獲得のゲームを楽しんだ。スキャンダルとなった、5度目の試みの予備審査での落選も、提出作品でみるかぎり、フーガにおける旋法的扱いと長7和音による終止(譜例1。審査員により3和音に訂正されている)、オーケストラ伴奏付き合唱曲《曙》における大胆な和声法(譜例2)は、《水の戯れ》(1901)、弦楽四重奏曲(1903)、歌曲集《シェラザード》(1903)といった、同時期の革新的な創作をすでに評価されていたラヴェルほんらいのものであると同時に、あえてローマ大賞獲得ゲームに(飽いたラヴェルが意図的に)規約違反をもちこんだ結果ともいえる。


ちなみに、ほとんどの評伝において、このローマ大賞のスキャンダルでパリ音楽院院長を辞任したとされているテオドール・デュボアにしても、じつはすでに定年退任が予定されていた。このスキャンダルの結果、次期院長の有力候補であった作曲科教授シャルル・ルヌヴーがはずれ、ラヴェルの師で音楽院出身者でないフォーレが院長に選出されたが、かつて音楽院の作曲科教授ポストを、マスネ退任後にほかならぬフォーレが獲得した事情を考えれば、ラヴェルを巻き込んだ院長選の意外な展開も、おそらくはフォーレが出入りしていたパリ上流階級のサロンにおける、有力政治家、高級官僚夫人たちとの親密な交友関係に起因するところの(当時にすれば一般的な)、サロンを中心にした音楽行政(ポリテクス)が背景にあると考えられる。
音楽機械・不能の愛
ラヴェルの個人的なセクシュアリティについては諸説がある。売春婦や周囲の同性愛者たちとの付き合いは、さまざまに語られてはいても不明である。
ところで、筆者は新ウィーン楽派の伝道師でもあるルネ・レボヴィッツ(1913-72)による、なんとも無国籍なラヴェル作品の怪演を気に入っている(A Portrait of France, Chesky CD57)。《ボレロ》の複調的カコフォニー(不調音)による永遠に旋回する音色のメリーゴーラウンド、《ラ・ヴァルス》の自動演奏機械(オルケストリオン)の奇妙なアコーディオン的強弱による、悪趣味すれすれのデフォルメの果てに、暴力的な破局(カタストロフ)へと正確に到達するさまは、ラヴェルのセクシュアリティと二重写しに、音楽機械の不能な愛の行為すら連想させる。
生命という時間性の創造から、機械(メカニズム)という生殖不能でありながら、永遠に複製を継続する行為への視点の移動は、芸術の名のもとに、同時代性という永続的な祝祭の日々を生み出しつづけるのであろうか。
回路・横断
ドビュッシーの音楽にみるような、瞬間に依拠する断続的な形式に対して、ラヴェルの音楽は、しばしば同一のリズム・パターン(舞踊的リズムによりながらも、かならずしも身体性を喚起させない、機械的な連続・不連続)による回路(サーキット)としての構造が、発展のないスタティックな形式を保証するともいえる。
たしかに瞬間の死ともいえるエロスの閃光が、あるいは虚構としての再生のためのタナトスが仕掛けられているとしても、ラヴェルの音楽では作品の個的な価値よりも、毎回の意匠(モード)の変換によりながら、けっきょく、回路としての創作ゲームが優先される。ラヴェルの父、ピエール・ジョゼフ同様に、怪しげな発明家・技師として、いっぽうでは生死を賭したギャンブル=ゲームに興ずるのである。
また作品ほんらいのオリジナリティにしても、《ラ・ヴァルス》に特徴的なように、ピアノ独奏、ピアノ二重奏、さらに管弦楽という形態が、かならずしもオリジナル(原曲)とトランスクリプション(編曲)という関係として生じるわけではない。行程的には、たしかに2つのピアノ稿には、管弦楽化という高度なテクノロジー実践のためのプレ・オリジナル的位置づけがあるとしても、それゆえにこそ管弦楽化にかんしてもまた編曲としての、相互的な創造行為の横断・越境(トランス)が問題とされるのである。
ラヴェルの音楽の意味は、バッハからストラヴィンスキーにいたる──今日のポピュラー音楽とも共通する──創造過程としての原曲と編曲の関係を提起しつつ、さらに今日における創作の意味をも照射している。
パリ国立高等音楽院における、オリヴィエ・メシアン(1908-92)の教育活動は、37年間(1941-78) におよぶ。当初1941-47年に和声クラス教授として、また1947年以降は当時の音楽院院長クロード・デルヴァンクール(1888-1954)により任命された分析クラス教授としての教育活動が知られている。後者は「音楽美学・分析」(-1954)、「音楽哲学」(-1961)、「音楽分析」(-1968)と名称を変えながら、メシアンのもっとも知られた教育活動として中核をなすものといえる。作曲クラスを指導した期間が、メシアンの教育活動の最後の時期(1967-78)にすぎないことは意外に知られていない[註1]。
3期にわたる教育活動は、結果的にそれぞれ音楽行政上のできごとと関連すると考えられよう。1941年の和声クラス教授就任は独軍占領下、ユダヤ系教授アンドレ・ブロックの罷免にともなう結果であり、1947年の「音楽美学・分析」クラスの創設は、和声クラス教授としてかならずしも成果を出すことのできなかったメシアンほんらいの長所を生かす選択であったと推測される。またレイモン=ガロワ・モンブランにより1966年に任命され、67-68年の「音楽分析」クラスの最後の学期と重複しておこなわれた作曲クラスにおける最初の教育活動は、1968年の5月革命に起因する音楽院の制度改革と関連する。
以下、メシアンの教育活動を概観しつつ、必要におうじてメシアン自身の創作活動との関連性にも留意しながら、フランス近・現代における作曲専門教育の歴史性について若干の考察を試みたい。
◎書法(エクリチュール)の教育
パリ高等音楽院の設立以来の教育システムの中心は、楽器の実技教育はとうぜんとして、さらにソルフェージュ教育と和声法・対位法(フーガ)からなる作曲書法学習(エクリチュール)であるといえよう (とうぜんながらソルフェージュ教育と作曲教育は今日にいたるまで、緊密に関連した歴史的経緯がある) 。
19世紀フランスにおける作曲教育の目標はオペラ作曲家の養成にあり、「ローマ大賞」にみられるように音楽院での最終コンクールは、あたえられたテキストによる劇的情景としての《カンタータ》の作曲を実践するための、声楽的声部書法としての和声・対位法(フーガ)、さらにオペラふう管弦楽法の修得が最優先課題であった。今日では多少理解しがたいかもしれないにしても、フーガ作曲の成果がつねに作曲科修了の、あるいはローマ大賞の予備試験の課題となるのは、オペラの重唱・合唱の書法の実践としての必要性ゆえなのである。
これらの歴史的慣習にもとづく独自の教育体系は、1905年、例外的に音楽院の出身者でないG. フォーレの院長就任による、書法クラスと作曲法クラスの分離や、音楽史クラスの創設をはじめとする制度改革にもかかわらず、維持されつづけたといえる。
ところでローマ大賞受賞(入賞)者でもないメシアン(2度の試みは失敗に終わった)独自のキャリアは、音楽院ほんらいの歴史性と複雑に交差しながら展開するのである[註2]。
1919年以来音楽院で学んだメシアンであるが、1926年に和声法の2等賞、さらに対位法とフーガ(1926)、ピアノ伴奏法(1928)、音楽史(1929)、作曲法(1930) での各1等賞獲得は、M. デュプレのオルガン演奏と即興クラスでの1等賞獲得(1929)において、はじめて総合的な成果をみる。H. ビュセールの作曲クラスを中心とするローマ大賞作曲家たち(H. デュティユーらに代表される)と異なり、P. デュカの作曲クラスからオルガ二スト(教会音楽家)へ、というメシアンのキャリアは、カトリック信仰によるというよりも、ある意味、音楽院における伝統的学習のもたらした偶然ともいえる。
◎伴奏法クラスとオルガ二ストの伝統、あるいはミュジシャン・コンプレ
「そして十六か十七のころ、私の和声の先生だったジャン・ギャロンが、オルガンを勉強するために私をマルセル・デュプレに紹介してくれました。私がカトリックだったからというのではなく、私のなかに即興演奏の才能を認めたからなのです。当時わたしはピアノでの伴奏のクラスの賞を得ていました。このクラスでは旋律課題に和声をつけることだけではなく、初見(デシフラージュ)やオーケストラの総譜をピアノで弾くことなどもやったのですが、旋律課題が鍵盤上での即興の重要な部分を占めていました。そして私がこの方面で才能を示し、オルガンという楽器が本質的に即興向きのものであるため、オルガンのクラスに入れたわけなのです」[註3]
伴奏科(正式にはピアノ伴奏科 Classe d'accompagnement au piano)についても、同様に音楽院の歴史的な教育制度と重要な関連がみられる。今日理解されるピアノ伴奏という意味と異なり、伝統的な総譜視奏の訓練(accompagnement pratique)と、ほんらい和声法クラスにおける伝統的な通奏低音法の実施の学習過程としてあったaccompagnement d'harmonieをまとめ、「伴奏科」クラスが新設されたのは1878年のことである。1880年に1等賞を獲得たドビュッシーが、はじめてその才能を公式に評価されたのもこの新設クラスにおいてであった。
オルガン・クラスとは別に、ピアノ伴奏科では初見視奏、総譜視奏や通奏低音法のみならず、教会音楽家=オルガ二ストの伝統的な修練、必要におうじてコラールの和声付け、前奏や間奏の即興と移調の技法などが、かたちを変えつつも基本的な課題とされてきた経緯についてはあまり知られていない[註4]。
とうぜんながら高度に実践的なそのあり方は、バッハに代表されるようなバロック以来の「完全なる音楽家」ミュジシァン・コンプレ(musicien complet)の伝統の中核をになうものなのである。
こうした過程からメシアンが1931年以降、聖トリニテ教会オルガ二ストとしての半世紀以上にわたる職歴と、パリ国立高等音楽院での教育活動や自身の創作活動を総合していったところに、単純にカトリック信仰のみに帰することができない経緯があることをじゅうぶんに理解する必要がある。
◎楽曲分析と作曲法・その歴史性について
音楽院における作曲専門教育と書法クラスについてすでに述べたが、19世紀前半には音楽院教授A. レイハ(ライヒャ)に代表される、既存の作品の分析による作曲法の分類から創作を学ぶ方法論が重要であった事実を知る必要がある[註5]。20世紀初頭のV. ダンディ『作曲法講義』(1903-50)にいたる、こうした伝統の延長線上にメシアンの「音楽分析」クラスのあり方を規定するべきであろう。そこでは従来から無批判に語られすぎるきらいのあった、伝統の見直しや前衛音楽の最前線としての評価のみでは語れないものがある。
メシアンは、M. エマニュエルの音楽史のクラスと、デュプレのオルガン即興演奏から、古代ギリシアの韻律法(メトリック)に関心をいだいたと語っている。さらにヒンドゥー(インド)のリズムにも興味の対象をひろげてゆく背景には、近代フランス特有の異国趣味(エキゾティスム)、あるいは植民地主義(コロニアリスム)すら想像できる。しかしながらこれらは、1940年代に作曲された《世の終わりのための四重奏曲》(1941)、《アーメンの幻影》(1943)、《幼子イエスに注ぐ20のまなざし》(1944)から《トゥランガリラ交響曲》(1946-48)をふくむトリスタン3部作にみられる、カトリック信仰とシュールレアリスムの臨界閾同様に、『わが音楽語法』(1944)に分析可能な作曲技法としてまとめられた帰納的な原理における、素材の水準を語るにすぎない。なによりもここで追究されているのは、作曲の方法論であり、それらは「分析」という過程において顕在化するのである。
6年間で終わったメシアンの和声法クラスからは、Y. ロリオとP. ブーレーズという2名の1等賞受賞者しか出なかったにしろ、クラスでは常時、あきらかに和声学習の領域を逸脱しながらも、さまざまな作品の分析がおこなわれていた。
同時期に音楽学者G. B. ドゥラピエール宅でおこなわれていたメシアンによる私的な分析講座でも、メシアンはブーレーズ、S. ニッグ、P. アンリといつた和声クラスの生徒たちに、バルトーク、ベルク、シェーンベルクやストラヴィンスキーと自作品を中心に、新たな音楽的興味と知識をあたえていた。こうした新しい音楽技法の受容が、分析をつうじての作曲技法の分類・実施という手順でおこなわれたところに、メシアンと伝統的な作曲技法の修得の方法論との一致がみられる。やや遅れて開始された、R. レイボヴィッツによる新ウィーン楽派の音楽と十二音技法についての私的講座が、メシアンの生徒たちを本格的な音列技法へとみちびく[註6]。
やがてダルムシュタット(1950-53)ほかでの、教育活動の広がりと同時に、さらに集中的な音楽分析による過去と現在の音楽のあり方の探究が、パリ国立高等音楽院でのメシアンの「音楽分析」クラスにおいておこなわれる。
◎前衛・秘教(1949-1960)
1951-52年度のメシアンの音楽美学・分析クラスの聴講生リストにはシュトックハウゼンやクセナキスの名前がみられる。こうした戦後の前衛音楽の中心となる若い作曲にたいする影響は、メシアンの啓かれた音楽思想と教育の証として、しばしば語られてきた。たしかにシュトックハウゼンはメシアンのピアノのための《音価と強度のモード》(1949)を1951年のダルムシュタット現代音楽講習会で聴いて興味をもち、1952年(1月以降)の短期間、パリ国立高等音楽院のメシアンの音楽分析クラスに登録したものと思われる。しかしメシアンが語るように当時とりあげていたモーツァルトのアクセント法がシュトックハウゼンにあたえた影響はきわめて限定的であるし、むしろシュトックハウゼンがフランス国立放送局で制作した実験的なミュージック・コンクレート作品《エチュード》(1952)と同時期に制作した、メシアンの《音色─持続》(1952)の成立の経緯のほうに関心がもたれる。《音価と強度のモード》は、3つのモード=12の音高と24の持続(音価)、12のアタックと7つのダイナミクス(強度)を組み合わせ、高・中・低音域でそれぞれの単音が特定の音高、音価、アタック、強度をそなえた3分半ほどのピアノ曲であるが、ブーレーズやシュトックハウゼンらに強い影響をあたえ、結果的に全面音列技法の実現を加速化したのは事実であろう[註7]。有限な人間にあってはリズム=時間の分割の試みをつうじてのみ、初めも終わりも継起もなきもの「本質的に永遠なるもの」を希求することができるというメシアンの音楽思想が、その技法的側面において、1953年以降のシュトックハウゼンの電子音とテープ操作による新たな創作原理を暗示したといえる。ドイツに帰国後に制作されたシュトックハウゼンの2つの《電子音楽習作》(1953,54)において試みられたのは、純音とノイズ、時間と可聴形式をめぐる、伝統的音楽では実現できなかった理論的な作曲の新たな方法論であったといえよう。さらにシュトックハウゼンは電子音楽制作の経験を前提に、ドビュッシーやウェーベルンの音楽の新たな評価を試みるのである[註8]。
メシアンのカトリック的・秘教的ともいえる創作と、戦後の若き前衛作曲家たちとの関係が、技法的・歴史的な一種のねじれをともないながらも、1950年代をつうじて豊かな創意と成果を生み出したのは事実であろう。またメシアンにおいてこの時期は、自然界の現実音=鳥の歌の採集・変形・編集といった過程と作曲手法の一致から生み出された《鳥の目覚め》(1953)、《異国の鳥たち》(1956)、またその集大成としての《鳥のカタログ》(1956-58)から、時間(持続)における数的神秘論、鳥たちの歌や大自然の音響のノイズを思わせる複雑な複合音の彩色法による《クロノクロミー》(1960)にいたる豊穣な創作時期でもあったのである。これらの作品でもちいられた手法についても、《異国の鳥たち》がミュージック・コンクレートや電子音楽における音源と加工・編集の過程を思わせる反面、ヒンドゥー音楽に由来するかの《鳥の目覚め》の真夜中から正午にいたる現実的時間と、《クロノクロミー》における音楽的時間の持続(音価・リズム・韻律)による再構成が対峙することなどからは、メシアンほんらいの関心と前衛音楽からの複雑で屈折した影響関係がみて取れる。
◎知の継承
メシアンはみずからをカトリック信仰にもとづく作曲家にして教会オルガ二ストと定義し、宗教的想像力を起点にして、永遠の象徴である限定と不可能性としての「移調の限られた旋法」「逆行不能リズム」「均斉置換(permutation symétrique)」などの作曲技法をもちいた秘教的創作をおこなったと考えてよいだろう。
オルガンの音響は、その宗教的イメージと同時に、近代の慣用的、限定的な音律から逸脱する、複雑な倍音構造によって、メシアンの前スペクトル的な音響的発想[註9]を支援しているし、また独自の時間論は戦後の前衛音楽における時間と形式の再考にもかかわりながら、脱西欧的な視点をも含むといえよう。
しかしながらすでにみたように、古代ギリシアから中世の音楽論、そして「アルス・ノヴァ」からルネサンスにいたる定量的=合理的記譜法にもとづく音楽技法の延長線上に、みずからの音楽を分析的に再構築するメシアンの姿勢は、あくまで西欧的知の伝承と深くかかわるものである。そしてこれらの「知」は、さらに継承されるべきものとして、(分析をつうじて)再発見されねばならないものでもあった。メシアンにおける教育活動とは、職能としての音楽家と同時に、知の継承者としての音楽家の象徴的表現でもあったのである。
さらに18世紀以前には伝承的な職制にすぎなかった作曲と演奏を、技術と様式の名のもとに教育制度にとりこむことに成功したのが、19世紀から20世紀初頭にかけてのパリ国立高等音楽院の業績(アカデミズム)であるならば、メシアンという存在はまさに、継承されるべき音楽における、制度としての知の実体化の例証として考察されなければならない。
註1 筆者は1977-78年のメシアン最後の学年に在籍した。筆者の経験では作曲クラスにおいても、メシアンの主たる関心事は「分析」であった。
註2 ドビュッシーは3度目にして受賞、ラヴェルが5回失敗し、ラヴェルの師フォーレはそのスキャンダル(1905年)を、前院長Th. デュボアの退官をうけての次期院長選に利用し、音楽院院長に就任した。ローマ大賞は、この制度にまつわる作曲家たちの反逆の伝説と相反して、ベルリオーズ以来、つねに彼らの最大の関心事であった。
註3 『オリヴィエ メシアン その音楽的宇宙──クロード・サミュエルとの新たな対話』戸田邦雄訳、音楽之友社。原題はMusique et couleur (音楽と色彩)、また本稿のタイトルにも引用した「Le savoir transmis(知の継承)」の章は、邦訳では「教育活動と弟子たち」と意訳されている。
註4 戦後(1949年以来)、N. ブーランジェからH. ピュイグ=ロジェにいたるピアノ伴奏科教授はオルガ二ストである。筆者はピアノ伴奏科でピュイグ=ロジェに最後の3年間(1977-80)を学んだ。音楽院退官後の女史の東京芸術大学客員教授としての業績については、船山信子編『ある「完全な音楽家」の肖像──マダム・ピュイグ=ロジェが日本に遺したもの』(音楽之友社)を参照。
註5 小鍛冶邦隆『作曲の技法──バッハからウェーベルンまで』(音楽之友社)の序章参照。
註6 のちのブーレーズの過激な言説にみられるように、メシアンとレイボヴィッツ両者の私的講座のあいだでの生徒たちの音楽的意識の亀裂が、戦後のフランス現代音楽に無視できない影響力を行使してゆく。
註7 メシアン自身の《音価と強度のモード》についてのひかえめな評価にもかかわらず、同曲のモードと発想をもちい、1951年にブーレーズは2台のピアノのための《構造1a》で全面音列技法を試みている。
註8 シュトックハウゼン「ウェーベルンからドビュッシーへ──統計的形式のためのノート」(1954)、『シュトックハウゼン音楽論集』(清水穣訳、現代思潮社)
註9 1967-68年度のメシアンの作曲科クラス初年度に、スペクトル楽派を代表するトリスタン・ミュライユ、1969年にはG. グリゼーが登録している。
(本稿は、『ベルク年報[12]2006-2007』に掲載された拙稿を一部改稿したものである)
1950年代の戦後日本現代音楽史は、ヨーロッパ前衛音楽のはるかな響きを共有しながら、解き放たれた空想の刻(とき)を生きる。
戦時の音楽文化統制という実体のともなわない制度が同時代の音楽におよぼした影響は、当時の音楽的水準ゆえか、音楽的実質とはけっして共振しえなかったと考えてよいだろう。
戦後という、その外延に、前衛・反逆の歴史が刻まれるというのも、不可思議な物語=歴史(ヒストリー)の、さらなる逸話(エピソード)であろうか。
戦後の創作史は、いうまでもないが、さまざまな同人会的グループによる作品展がその中心になる。こんにちもっとも知られている「実験工房」のようなマルチメディア的な運動は、その外延の文化的多様性により、音楽創作の歴史性からまさに逸脱した条件を得るところから出発している。武満徹に代表される「現代音楽」──その「現代」という時代性は、同時代の文化全般にわたる共時性(コンテンポラリー)のもとで、芸術音楽の歴史性から自由になり、その出自と評価にたいして自己基準を設定することが可能となったことにより獲得されたと考えてよいだろう。
◎制度・アカデミズム
ところで、芸術音楽の歴史性とは、いうまでもなくヨーロッパ社会における階級社会性を反映するものである。
日本の洋楽移入は、とうぜんながら近代国家としての文化政策と市民文化の擬似的配置に、その根拠がもとめられる。そこでは制度としての音楽が必要とされるのは必然である。19世紀以降のヨーロッパ市民社会が、制度としての芸術音楽の拠点として、音楽教育機関の整備を意図したように、日本では明治時代以降、東京音楽学校(現在の東京芸術大学)がその中核におかれたわけだが、制度としての音楽文化のなかでも、創造の拠点とするべく作曲科が設置されたのは、1932年であったということが、日本の音楽文化の状況を表しているといえよう。
さて、戦後の日本現代音楽史においてしばしば、東京芸術大学作曲科という唯一のアカデミー(制度)の歴史が、それに「対する」傍系・逸話としての反動の歴史のなかでのみ、記述されている点に注目したい。ここには、こんにちにいたるまで、傍系があたかも中心をしめるような擬似的配置のもとに、反アカデミズムの神話を生みだした人びとの物語(ヒストリー)がある。
◎舶来と土着
ヨーロッパにおける新旧の音楽文化の推移は、おもに教会音楽、オペラ、交響曲、室内楽、歌曲といったジャンルの枠内でおこなわれてきた。
1950年代のヨーロッパ前衛音楽が、こうしたジャンルの枠組み(ジャンル特有の、あるいは共通する形式や語法)をほぼ踏襲しながら(あるいは意図的に解消しながら)展開されたのは明らかであろう。こうした音楽創作におけるジャンル性は、19世紀以降の作曲専門教育における、各モデルとその分析、再創作という手順を反映している(とうぜんながら歴史的な作曲技法もまた、それじたい方法論として内在化する)。こうした歴史的な音楽創作の基準をあえて顧慮しないところに、「実験工房」のようなマルチメディア的創造の可能性が生じたといえるが、そこでは同時に、歴史的な創作原理との直接的な対峙はつねに回避されなければならなかったともいえる。あえていえばそこには制度(アカデミズム)の思わせぶりな影さえ暗示されていればよかったのである。こうした芸術運動を支持したのは文学、美術、映像作家たちであったが、彼らからすれば、音楽という実態の定かでない分野を巧妙に活用したというところであろうか。
反面、演奏芸術については、日本においても、相当ていどにヨーロッパの音楽文化との共時性が反映した歴史がみられる。その中心的存在としての、戦前の東京音楽学校のお雇い外国人教師による教育は、戦後の実技教育に1930年代の新即物主義(ノイエ・ザハリヒカイト)の影響化にある演奏という遺産をのこす結果となった。またそうした旧世界からの舶来文化=精神的風土に対し、戦後の桐朋学園やヤマハ音楽教室等の、日本文化的特性に根ざした、いわば土着的方法論が、新世界(アメリカの技術主義と大衆性)を視野に入れながら対峙することになる。
創作においても「ヨーロッパ対日本」といった、前衛の精神主義と日本的感性=慣用法が問題となる。
◎現代の音楽・音楽の現代を語る人びと
「実験工房」にみるまでもなく、戦後の創作運動の主導者たちは、創作者であるより運動のオーガナイザーであることが多いが、場合により(武満徹から細川俊夫にいたる系譜にみられるように)、これらを創作者がしだいに兼ねていく状況もみられる。これらは、戦後の多くの作品発表活動の延長線上に、こんにちも主流をしめる同人的活動の水平的水準に比較して、メリハリにとんだ同時代性(コンテンポレイニティ)を特徴とする。
1990年代以降こうした創作運動は、さらに若手作曲家を中心として、前衛以降のヨーロッパ現代音楽の潮流を学ぶという(あたかも1950年代を再現するかのような)講習会的組織に重点を移していくともいえるが、ここでは戦後の音楽学(アカデミズム)の教育をうけた批評家=音楽学者たちが、彼らとジャーナリズムとの仲介をひきうけ、みずからもジャーナリズム・企業体の磁場に周回軌道を合わせることになる。同時代性を基準とするかぎり、こうした批評家たちが、現代の音楽文化(消費)の主流をしめる、企業体主催公演や今日的な文化的イヴェントとしてのオペラ公演に、現代音楽の分野でつちかわれた、巧緻なその言説=レトリックをシフトするのもとうぜんといえようか。
◎伝統・アカデミズム
東京音楽学校作曲部は、戦争(戦時文化協力)問題について、その論点すら明確にするすべもなく、あいまいな人事の入れ替えののち、戦後1949年の教育制度改革により東京芸術大学作曲科となる。信時潔(1887-1965)や橋本國彦(1904-49)らの戦前・戦中の指導者たちによる、ほんらいドイツ音楽志向の強い教育方針が、下総皖一(1898-1962)や長谷川良夫(1907-81)といった彼らの継承者により受けつがれたものと思われるが、同時にパリ国立高等音楽院によって構築された、技術と様式の修得に特化した近代的教育を信奉する池内友次郎(1906-91)による、和声・対位法・フーガからなる作曲書法(エクリチュール)教育(註1)を根幹とする新たな流派(エコール)が参入する(これらの作曲書法教育の前提となる、パリ音楽院のソルフェージュ教育の基幹が整備されるのは、さらに遅れて1980年以降、戦前同様に外国人お雇い教師であるH. ピュイグ=ロジェを中心とした継続的改革ののちであった)。こうした戦前・戦後の伝統的な作曲専門教育にみられる流派(エコール)に、あたかも日本的な伝統芸能のあり方になぞらえるように、アカデミズム・保守性というあいまいな概念が重ねあわされているところが、こんにちにいたっても反動性という評価を温存する根拠となっているのであろう。
「前衛」というあきらかに時代的なファッション性に依拠する視点と、むしろさまざまな文化的テクストの織りなす歴史性から一定の基準で抽出される「アカデミズム」を、同列に比較することはほんらいむずかしい。しかしながら、その根拠のとぼしさが、前衛と反動の物語を織りなす意味でまた、歴史性といった視点を提供しているともいえようか。
◎同時代的(コンテンポラリー)な貧困
1970年万博以降、ある意味権威主義化した現代音楽は、1980年以降の多極化(グローバル化とも称されるが)と同時に、さまざまな同人会的作品展の氾濫による飽和的な状況を経過してきたといってよいかもしれない。個人的創作という究極のアンデパンダンの理念が、東京という都市文化における、無辜な祝祭の刻を生みだしたのだ。
いっぽう作曲という技術的手段は、高度に集約化された文化資本のまえに、その能率化と目的の明確性をもとめられることになる。アカデミズムという、いまだ唯一の学習形態にあって、若い作曲家たちは伝統的な音楽文化というあり方を、今日的にいいかえれば、「格差」と「下流志向」という観点から再度学習しなおすのである。20世紀以降の市民社会におけるマイノリティとしての「現代音楽」を大前提にし、「文化資本(いわゆる教養)には差別化機能がある」という伝統的(社会上層)概念を、「こんにちにおいてはもはや、文化資本には差別化機能がない」と反転させることによって伝統を無効化し、現代音楽の特権化という名の下層化(一般化)が進行する。それらはやがて、さらなる閉鎖的な階層化をもたらすことになる(註2)。
註1 本連載第9回「メシアン、あるいは知の継承(Le savoir transmis)をめぐって」参照。
註2 「例えば、日本でも、社会上層では「文化資本(いわゆる教養)には差別機能がある」と信じられていますから、子どもたちは進んで文化資本を身につけようとします。逆に、社会下層では「文化資本には差別機能がない」という考え方のほうが受け容れやすいので、子どもたちはむしろ積極的に文化資本を拒否するふるまいによって同集団の大人たちからの評価を期待します。階層が閉鎖的になると、子どもは階層内部的な評価を通じてしか「自身」を高める道がありませんので、子どもは所属階層のイデオロギー性をいっそう「濃縮」した仕方で体現するようになります。そのようにして、わずかな世代交代の間に、階層は急速に閉鎖的になります」(内田樹『下流志向』講談社、2007年、114頁)
本稿ではかならずしも、上記の引用テクストにおける文化一般の社会上層対下層の位置づけのレトリックを、音楽文化における伝統対現代性の問題に読み替えようとしているわけではない。むしろ言説の内部にある関係性の変化が、伝統的音楽文化においても、伝統性と現代性の反転を容易にひきおこすことがあるということを強調したい。
前回の連載では、ヨーロッパの歴史的音楽とはあきらかに異なる、日本の文化制度における統治としての音楽文化の特異性(あるいは不在)についてふれた。とうぜんながら移入文化である「西洋音楽」は、戦時においても、政治的プロパガンダ以上の意味性は獲得されることなく、またそれゆえ実質的な統制の対象ともなるべくもなかったように思える。
日本の戦後の現代音楽は、その出自を自由に選択できると同時に、同時代のヨーロッパ市民社会の歴史性を映す鏡像としての「前衛」を、あきらかに異なるコンテクストで引用することにより、その「現代性」を容易に獲得したといえよう。あとは発育不全のアカデミズムという、実質性のない領域のイメージを対比的に操作すればことたりた。
しかしながら歴史的体験としての「戦時」が現実であるかぎり、やがて作曲家の想像力の極性に作用する瞬間もとうぜん訪れるであろう。
◎レクイエム・レクイエム
武満徹と三善晃の《レクイエム》がある。それぞれに異なる時代性(1950年代後半と70年代初頭)に作曲されたこれらの作品については、作曲者自身によって作品の成立と戦時との関係が明らかにされている。
武満徹の出世作、《弦楽のためのレクイエム》(1957)の場合、想起されるのは、この作品に直接言及していないとしても、「暗い河の流れ」という作曲者自身によるエッセイである。このよく知られたエッセイは、「私にとって音楽がはじめての〈他者〉として現れたのは終戦に近い、一九四五年の夏であった」とはじまり、ジョセフィン・ベーカーのシャンソン《聞かせてよ、愛の言葉を》との邂逅という有名なくだりへとつづく。そして終戦=敗戦としての戦後という状況(「私たちは、ひとりひとりの暗い河の流れに身をまかせるより他になかったのだ」)のなかで、作曲家としての出発が語られる。
武満がさらに「1960年、安保の批准成立によって、私の青春は終わった」と書くことにてらせば、《弦楽のためのレクイエム》が映していたものもまた、特定の対象への弔いというよりも戦時と戦後の精神風景としての時代へのまなざしであったのはいうまでもないであろう。
いっぽう、1971年に作曲された、三善晃の混声合唱とオーケストラのための《レクイエム》について、三善自身が書いた文章には、「あんなにも近く、親しく、私もその隣にいたという意味で平易ですらあった死者たちの死に、地上のどのような希いも祈りも慟哭も届きようがないことをさとるためにしか、私は「レクイエム」の音を書き綴らなかったのだ」(《詩編》(1979)のための作曲者による解説)という一節がある。
戦争のさなかの身近な死の記憶たちが、四半世紀の刻をへだてて、作曲家の想像力のさなかに、あたかも「私の内部の祭りである」(上記解説)かのように激越で華麗な音響を解きはなつのである。
武満のエッセイ「暗い河の流れ」が朝日新聞紙上に掲載された1971年、たまたま2人の作曲家の「戦時」とそののちが出会う。「永久(とわ)の死者の平安(レクイエム・エテルナム)」などではなく、レクイエムという喪の葬祭──「レクイエム・レクイエム」として。
◎西方より
ふたたび50年代に戻ろう。
三善晃はフランス政府給費留学生として、1955年から57年にかけてパリに学ぶ。パリ国立高等音楽院和声クラスのアンリ・シャランのもとでの学習は、幸福なものともいえなかったのだろう。
「本能的な音楽的創造性と構築性」(矢代秋雄)にめぐまれた作曲家にして、アカデミズムという名のヨーロッパ文化の歴史性からうけた拒絶は、やがて彼の創作の拠点としての文化と歴史性の問題に漂着するであろう。1974年以降、桐朋学園大学学長として教育の分野に活動をひろげ、また多くのアマチュア合唱団との出会いから生まれた豊穣な合唱音楽や、伝習的なピアノ教育に一石を投じようとするMiyoshiピアノ・メソードの開発などの創造的な軌跡のうちにこの作曲家がもとめたものは、プロフェッショナリズムとしての市民的教養主義にもとづく、連帯によるコミュニティへの道程であったのかもしれない。
1995年に桐朋学園大学学長を辞任したのち三善は、《レクイエム》三部作(1972~84)と対応する、《夏の散乱》以降のオーケストラ四部作(1995~98)をつうじて、一貫して戦争体験にこだわる作曲家という世間的評価のもと、華麗な創造の軌跡を描く。同時に東京文化会館長(1996~2004)として、芸術創造と行政とがせめぎあう場にかかわることで、彼は再度、コミュニティとしての音楽文化という「制度」を生きようとするのである。
大学の学長として夢見た、音楽専門教育における伝承性(徒弟制度)からの自由と自治(註1)も、市民的連帯による文化創造も、ヨーロッパにおける伝統的な文化的統治につらなる芸術音楽のあり方とは、あきらかに異なるものである。けっきょく、創作技法じたいに内在する知のヒエラルキーとしての、歴史的音楽の実態を超えて、さらなる自由を獲得することはできない。接ぎ木された「自由」は、やがて固有の文化において新たな「制度」を構築するのである。
◎東方から
1970年の万博は、まさに文化資本としての音楽文化の新たな様相を予示したともいえる。三善晃が音楽という旧制度に教育からかかわろうとしたのと同時期に、武満徹は西武劇場のオープニングとして、それ以降20年間におよんでつづくことになる「今日の音楽」(1973~92)のプロデュースをおこなう。パルコに代表される都市文化の記号としての「東京」を仕掛ける複合的商業資本にとって、むしろ伝統的音楽と等価な(あるいは反転としての)現代音楽という構図こそが、より刺激的であったのであろうか。
武満という、異なる伝統的音楽文化にたいして等しい距離(ディスタンス)(註2)をとりながらアプローチする、自己選択的なアマチュアリズム(消費主体)としての作曲スタイルは、商業資本のあり方とも共振しやすい。そもそも生涯を多数の舞台・映画音楽(商業音楽)の作曲家としても生きたこの作曲家にとり、現代音楽とはその延長線上の創作として、時代と事実上、きわめて共時的な関係を保つ領域なのだ。
《弦楽のためのレクイエム》のいっけんつたなくみえる初期の書法も、映像におけるカット割りを思わせる構成(形式)や、カメラ・ワークにもなぞらえられる音楽的テクスチュアの濃淡にもとづくものといえよう。これらはたしかに内面的な表現というより、前掲のエッセイにも現れる〈他者〉としての音楽的オブジェとの距離のとり方ともいえる。1980年代以降の豊穣なオーケストラ作品群も、こうした無数のかけがえのない夢の散乱とも思える、音楽的断章(フラグメント)としての高価なオブジェ=コレクションなのである(註3)。
武満の音楽には、ヨーロッパの芸術音楽への自由で誤解に満ちたまなざしがある。現代音楽という商品記号は、こうした憧れと、たまさかの所有の夢のうちに、高度資本主義による文化戦略という、新たな統治を生み出す迷宮のネットワークの一端をつむぐのである。
註1 「三善─学生との精神的なつながりでしょうか。学生を信頼してみようと自分でも思ったし、学生のなかには、あの頃は三善の存在があって、いい時代に出くわしたな、と今、言ってくれる人もいます。
丘山─つまり学生にとっての「学長」のあり方、関係性、それまでとはまったく違うもので、そこにある一種のシンパシーみたいなものが生まれた、その幸福ですね。
三善─そう。それまでは、先生と生徒という形式的な関係、位置づけに慣れていたでしょう? でも、ほんとは学生・生徒たち、とても敏感。そして、「みんなと一緒」というのを感じさせた。前にお話しした女の子の「みんながいたから、私がいた。だから良かった」という、あれね。
(後略)」(三善晃・丘山万里子共著『波のあわいに 見えないものをめぐる対話』春秋社、2006年、107頁)
註2 「むしろこの作曲家特有の「距離(ディスタンス)=関係」の認識というべきであろう。作品のタイトルとしても用いられる《ディスタンス》は、相反するものの相互の位置関係を見極める装置であり、また多数が「関係」において固有の生を生きる意味でもあるのであろう」(小鍛冶邦隆「ドゥブル・レゾナンス 武満徹のアンサンブル作品をめぐって」『武満徹 音の河のゆくえ』平凡社、2001年、55頁)
註3 武満の初期、および1980年代以降の一般的様式については、前掲拙論「ドゥブル・レゾナンス」を参照。
伊福部昭(1914~2006)の《日本狂詩曲》が作曲されたのは1935年であり、同年パリのチェレプニン賞を受賞、翌年にボストン初演された。フランス・ロシア近代音楽を中心としたスコアのみを情報源とし、そこからオーケストラの機能と響きを想像して作曲されたこの作品は、戦前の日本における管弦楽作品を代表する音楽のひとつであり、また戦後1953年に刊行された『管絃楽法』(註1)とともに、日本人作曲家が近代管弦楽というテクノロジーをいかに理解し、マニュアル化したかを示している。
◎オーケストレーションという作曲の技法
《日本狂詩曲》を聴いてみよう。そこでは主題や調的関係による形式といった、統辞的意味としての音楽構造がほぼ不在であり、一定パターンのフレーズの反復が、オーケストレーションのテクステュアの変化と対照性のみで、音楽的実質を生みだしているといってよい。欧米人には、素材の民族的特性よりも、音楽的構造にかんする異質性において、むしろエキゾティックに捉えられたと思われる。
さらに創作同様に伊福部の代表的な業績である『管絃楽法』は、リムスキー=コルサコフ以来の、ヴィドール、フォーサイスなど(とりわけ前者)による近代管弦楽法の著作を下敷きにした管弦楽法概論として、きわめて実用的なもので、こんにちにいたるまで戦後日本の作曲家に多大な影響をあたえてきた。音楽的創意はオーケストラのテクノロジーじたいから触発をうけ、ヨーロッパの伝統音楽にみられる音楽的発想と演奏実践としての歴史的管弦楽技法との矛盾に満ちた経緯をいっさい清算したところから創作を開始した時点で、あたかもバロック的な「機械仕掛けの神(デウス・エクス・マキナ)」であるかのように、管弦楽は作曲家に予定調和の恩恵をほどこすのである(註2)。
◎屹立する響きと馴致
松村禎三(1929~2007)の音楽は、師・伊福部の創作理念を受けつぎながら、やがて中国からインドにまでいたるアジア的な発想という、(抽象的な視点ゆえに)とらえどころがないほどの広がりをもち、工芸的ともいえる精緻な作曲法と管弦楽法にもとづく、すぐれて自省的な創作として、戦後日本を代表するものといえる。
1960年代の現代音楽シーンにおける創造的エネルギーの極点と思える《交響曲》(1965)や《管弦楽のための前奏曲》(1968)に聴かれる、ヨーロッパ的な倍音構造とは異なる、あたかも楽音とノイズと臨界域で生ずる独自の音響像(註3)からは、たしかに松村に多くの影響をあたえたストラヴィンスキー《春の祭典》(1913)における、ヨーロッパ音楽の異化としての先鋭的な構造化と共通するものもうかがわれる。
《管弦楽のための前奏曲》に聴かれる日本伝統音楽ともつうじる音程の揺れや音律、音価の扱いを模倣する管楽器の扱いは、やがてストラヴィンスキーの書法から暗示をうけたヘテロフォニーという名の擬似ポリフォニーと、オスティナート・ドローンという擬似ホモフォニーへと構造化をとげる。
いっぽうこの音響的に特化された音楽が、発端がどうであれ、あたかも近代的個の崩壊の過程を演算するかのように形式的発展をたどることから、われわれはいやおうなく、それが戦後日本社会における状況を反映する、あまりに文学的(私小説的)なあり方を示すことに驚くことになる。
こうして三善晃の音楽にも聴かれるように(註4)、しばしば能や歌舞伎といった伝統芸能を暗示し、またあるときは主情的な文学的ドラマでもある、仮想現実をめぐる演技的空間に、音楽はくりかえし纂奪される。、日本近代という固有の文化が封印された内部と、それらと密接にかかわる音楽表現形式として外部からもたらされた方法論とのあいだに、直接的な関連性をみいだすことはむずかしい。ともあれ表現者がほんらいの技法とはかけ離れたところでおこなう生々しい表出は、ある意味で表現主義的な様相をおびる。こうしたリビドーとしての自己消費型サイクルをもつ創作には、知としての音楽のあり方からとうぜん帰結される、創造原理じたいが内包する、統治としての文化というコードと、人間という不確かなあり方とのあいだで、たがいに侵犯を繰り返すあやうさはない。創造とは、はてしない自己表現の結果というよりは、「世界という構造と向き合う自己」という対になる構造から算出されるのである。
◎汎アジア主義というエキゾティズム
三善晃の《レクイエム》(1971)が、まさに戦中・戦後という日本近代の終焉としての弔いの儀式であるならば、万博以降、1980年代までのグローバリズムは、日本近代をアジア的多様性という視座から定義しなおしたものともいえよう。
松村禎三のピアノ協奏曲第1番、同第2番は1973、78年に作曲されたが、第1番における鎮魂(註5)としての御詠歌や、民族楽器の響きを模した第2番におけるピアノ書法は、あたかも想像上の汎アジア的なエキゾティズムという異界を、創造という虚構の劇場に移したものだ。
80年代を代表する作品として知られる西村朗の2台のピアノと管弦楽の《ヘテロフォニー》(1987)も、(かたや昭和後期、かたや平成バブルの予兆という時代意識の差こそあれ)松村の創造の軌跡なくしては生まれなかったであろうすぐれた音楽である。いっぽうでこれらの音楽は、東洋・西洋という従来のコノテーションが、管弦楽的音響の精密なデジタル的変換を介して乱反射した今様オリエント・オリエンテーション(東洋案内)ともいえる。
また、ふたりの作曲家自身が認めているように、これらの作品に認められる広義のアジア的宗教観念に、祭祀としての創造というアジア的統治にかかわる意識がかいまみられる点には、あらためて興味をおぼえる。
アジアという記号による無国籍なポップ・カルチャーの隆盛のもと、音楽が生まれる社会構造の基盤としての、歴史的なアジア的統治・文化様式を視野にいれながら、創造におけるあらたな展望は生まれるのであろうか?
註1 伊福部昭『管絃楽法』(音楽之友社、初版1953)。同書は1968年上巻として改訂され、同時に下巻が刊行、2008年『完本管絃楽法』として新版刊行。
註2 ベルリオーズ/シュトラウス『管弦楽法』(小鍛冶邦隆監修、広瀬大介訳、音楽之友社、2006)をみれば、18世紀から20世紀初頭にいたる演奏実践としての管弦楽法の変遷が、歴史的な作曲技法といかに具体的にかかわっているのか理解できるだろう。
伊福部『管絃楽法』にみられるような、歴史性を捨象した水準で自由に扱えるマトリックスとしての管弦楽法の位置づけは、戦後日本における「前衛音楽」という、そのほんらいの歴史的コンテクストから切り離された便宜的な位置づけと共通しているといえるかもしれない。本連載第10回「日本戦後日本音楽史──前衛とアカデミズムの逸話(1)」参照。
註3 管弦楽の音響構成ほんらいの基礎倍音(完全8度、5度)を完全4度や増4度に置き換え、中・高音域に部分音を密集させて、あたかも非整数倍音によるかのようなノイズ的な音響を生みだす。また頻出するユニゾンも、歴史的にもちいられてきた補色関係の楽器法を避けることで、結果的に倍音原理に収斂されない手法が本能的にもちいられている。
註4 本連載第11回「日本戦後音楽史──前衛とアカデミズムの逸話(2)」参照。
註5 松村禎三はピアノ協奏曲第1番の創作時に、くりかえしモーツァルトの《レクイエム》KV626を聴いたと、筆者に語った。
[著者プロフィール]
小鍛冶邦隆(こかじ・くにたか)
東京芸術大学作曲科で永富正之、松村禎三に学ぶ。在学中より指揮者・山田一雄のアシスタントをつとめる。同大学院をへて、パリ国立高等音楽院作曲科、ピアノ伴奏科でメシアン、ピュイグ=ロジェに、ウィーン国立音楽大学指揮科でスウィトナーに学ぶ。自作を含むプログラムで東京都交響楽団を指揮してデビュー以後、新日フィル、日フィル、東響、東フィルなどを指揮。1999年以来、東京現代音楽アンサンブルCOmeTのディレクター・指揮者として多数の現代作品を初演。「室内オーケストラの領域III」にたいして2003年度第3回佐治敬三賞受賞。またクセナキス作曲コンクール(パリ)第1位、入野賞、文化庁舞台芸術創作奨励賞、国際現代音楽協会(ISCM)「世界音楽の日々」ほかに入選。ベルリオーズ/R. シュトラウス『管弦楽法』邦訳監修や著書『作曲の技法──バッハからウェーベルンまで』(以上音楽之友社)、CD『小鍛冶邦隆作品集/ドゥブル-レゾナンス』(ALM Records)ほかがある。
東京藝術大学作曲科准教授、慶應義塾大学文学部講師。

photo. Philippe Gontier