音楽・知のメモリア (小鍛冶邦隆)
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトが、スヴィーテン男爵をつうじてヨハン・セバスティアン・バッハの音楽を知ったのは1782年という。ウィーン時代の創作には、たしかにバッハふう──というよりも、バロック様式の反映がみられる。 教会様式やオペラ・セリアなどにみられる伝統的な擬古的様式(バロック的対位法様式)が、交響曲に代表される器楽様式に直接的に影響を与えるという現象は、なにもモーツァルトにかぎったことではない。しかし前時代の通奏低音技法に支援され、韻律的に調整された歌唱的旋律書法を基本とする、18世紀後半に典型的なモーツァルトの音楽語法=古典派様式に与えた影響は、むしろ異なる様式を相対的にみる視点にこそ本質的な問題が含まれている。
内面性の反映としての創作
ウィーン時代後期の代表作、交響曲第39番から第41番の3曲が、1788年の6月から8月にかけて集中して成立しているのは周知の事実である。これらの作品には豊かな旋律性と同時に、対位法的な主題(動機)展開の技法にささえられた、大規模な調的統一による音楽形式(ソナタ形式など)が、多様な管弦楽的様式により、それぞれの特性をそなえながらも高い水準で実現している。
なかでも交響曲第40番ト短調K.550は、他2曲にくらべて、編成においてのみならず、音楽においてもより室内楽的な内面的で精緻な表現をめざしているといえよう(とうぜんながら同名調によるハイドンの交響曲第39番〔1768〕からモーツァルト自身の交響曲第25番K183〔1773〕にいたる先駆的様式がある)。
ここにみられる修辞的にも複雑な旋律法は、モーツァルト特有の半音階法に彩られた、近代的人間性の陰影の微細な推移を表現する和声法と結びつくことから、後世の創作モデルとなるような新たな表現領域を開拓したといえよう。そこでは作曲家自身の内面が、創作行為にリアルタイムで、過敏にまた過激に反映する作曲法として問題化されるのである。作曲行為は作曲家個人における、内面的な危機=発作(クライシス〔crisis,crise〕)のシミュレーションともなる。
作曲家の内面性の反映としての創作という近代的原理は、バッハの創作にみられた世界の構築性としての音楽モデルといかなる関係、あるいは相違を生み出しているのであろうか。
形式という知の橋梁
ところで交響曲(単一楽章から多楽章にわたるシンフォニア)にみられるような、テクストに構成を準拠しない大規模な器楽曲の創作を保証するものは、各ジャンル固有の様式の問題というより、共有される形式の関与といえる。
大規模な調的統一による音楽形式とは、ソナタ形式にみられるような、主に複(多)主題の提示・再現における調的対応(主調と近親調間)と、主題的素材の調的展開(より広範囲の調的推移)から構成され、たんなる時系列による連鎖的構成と異なり、重層的なパラダイム(規範)としての創作の原理を設定する、まさに形式全体に理性的視点から照射される啓蒙(enlightenment)的な構造性ともいえるものが、時代の文化と呼応しつつ試みられたともいえる。
しかしながら、この制度的ネットワークは、各所に個人的事情による断絶と混乱が蓋然的に生じる可能性を残している。その理由については、今後の連載でより具体的にみていくつもりであるが、ここではモーツァルトのト短調交響曲から、いくつかの実例をさがしてみよう。
ふたたび音律と調律の問題
前回(第3回「セバスティアン・コード(3)」)、バッハの創作における音楽的実存としての音響現象と、身体性をつうじての音律・調律と創作・演奏の関係についてふれた。
モーツァルトの場合はどのような関係がみられるのであろうか。
1)第1楽章展開部は、提示部最終小節から4小節の木管アンサンブルの短い移行句(100~103小節)をへて、提示部冒頭の主調ト短調から半音低い嬰へ短調で第1主題が開始される。18世紀において一般的であったと思われる5度圏からなる調領域(5度圏表参照)を前提にすれば、相互の遠隔調としての関係はきわだっているといえる。しかしながらむしろ、きわめて優れた聴覚の持ち主であったと推測されるモーツァルトにおいては、これらの5度圏から生じる相互関係よりも、提示部冒頭の第1主題が半音低く再提示される事実のみが、作曲家の内面の異常な生理(空虚感)に結びつく。とうぜん一般的な聴衆に感知されない水準で、創作が進行するのである。
2)第4楽章展開部では、第1主題による模倣的展開(4声ストレッタ)により、ト短調から嬰ハ短調を往復する反復進行(ゼクエンツ)が、5度圏の対極をそれぞれ15小節(161~175小節)と11小節(191~201小節)で結ぶ。これら5度圏の急速な移動(〔c-〕g-d-a-e-h-Fis〔fis〕-cis。5度圏表参照)は、過密な対位法的反復進行モデルにおいて実現される、転調というより音響現象の異常な推移から、一種の錯乱ともいえる精神下のできごとを象徴するともいえる。
こうした音律・調律の5度圏による安定的回路を遮断する危機的発作は、モーツァルト自身の身体的な衝動ともいえるが、これらの経緯がやがて、以下のように構造化され、展開部という形式機能を形成する水準において、精神作用としての音楽という近代が始まるのである。
3)第1楽章展開部の嬰へ短調の主題再帰以降、二重転回対位法によるバロック的反復進行(115~132小節)が、長期的に安定した調的推移(e~d、C~B)を生み出すのに対し、展開部後半の保続部分ふう推移(134小節以降)は、一瞬だけニ短調と遠隔調である変ロ短調の、聴覚的な鋭い痛覚ともいえる異名同音ふう転調を経過する(139~140小節)。その後の属保続音上の再現部への推移(153小節~)・導入(164~165小節)は、後者が展開部冒頭同様の木管アンサンブルによる移行句により、主題再現冒頭が隠微された特殊な修辞的意味を付与されている。
4)第4楽章展開部の急速な5度圏移行に囲まれた中央部分の16小節(175~190小節)にわたる、主調ト短調の対極点(5度圏表中の点線参照)としての嬰ハ短調の鋭い音響的対比は、モーツァルトの鋭敏な聴覚にとっては、ほとんどノイズ的な外界との軋みとしての、精神の緊張を生み出すともいえよう。
バッハおいては、創作・演奏の拠点としての特定の調選択とその推移が、モーツァルトにおいては、あくまでも相対化、および移行を前提とした通過点の意味に変化している。モーツァルトの鋭敏な聴覚と、自身が保持していたと思われる5度圏の絶対音的基準からのずれが、創作においての危うい均衡を生みだす。
というのは、ここでいう音律はむしろ、不確定な音響現象としての本来性において認知されているともいえるが、18世紀全般の基準とも考えられる、中全音(ミーントーン)などの使用における(嬰・変記号3つていど以内の)主調範囲の限定手段としての、調律における自閉的な5度圏の構築は、調的構造の均等化=(絶対音高による)平均律への移行を必然化するのである。開かれた音響現象としての本来の音律の意味は、概念的なオクターヴの均等な分割による調律法=平均律という、音響学的な暴挙ともいえる制度(構造)の背後に、その闇をさらに深くする。
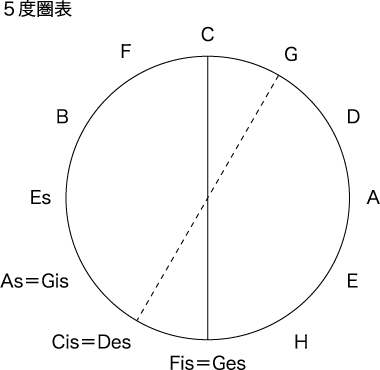
音像の錯乱
さらにモーツァルトの聴覚の特異性に注目しよう。
有名な第3楽章のメヌエットは、このジャンル(舞曲)としてはやはり異例な対位法的書法で貫徹される。しかしながらここでは、対位法という網状的管理技術よりも、本来の音響現象としての異質さに目を向けてみよう。
メヌエット主部前半は、主に両外声2声の対位法を中心として、控えめに内声部が充填されるていどの、異例のむき出し(déplouiller)の書法といえる(ハイドンの初期交響曲にも、通奏低音で補填されない両外声のみの書法、という前例がある)。小節構造上の韻律(メートリク)の3+3+4+4という(舞曲にあって例外的な)不規則性は、主部後半(15小節以降)の最初の9小節間(3+3+3)にもみられるが、その後は4小節構造に落ちつき、最後の結句(40~42小節)のみ、ふたたび3小節となる。
主部後半最初の9小節間はメヌエット主題による弦バス低声部(Vla、Vc、Cb)に対し木管上声部(Fl、Ob)、ヴァイオリン2部による対位上声部は木管低声部(Fag)で重複されるため、主要2声部は対声部について相互に超過現象(オーヴァーラップ)をひきおこすともいえよう。
このように本来の音響的な上下関係が、特殊な対位法的・楽器的書法で、意図的に混乱させられる状況がみられるのである。バス声部に転回したメヌエット主要主題に、上声部の対位声部を与えるという伝統的な対位法的書法において、モーツァルトの異例ともいえる聴覚の錯乱として、倍音的に上行する音響イヴェント(音律)が意図的に混乱させられるのである。
もし作曲家に近代的な意味で精神性というものがあるのであれば、これらは主体とは異なった水準で、精神現象の亀裂が実体化・構造化されたものともいえよう。音楽は知の基本モデルから特化して、近代的文化制度としての知の均質化を回避しながら、結果的に作曲家の主体性を解体しつつ、新たな暫定モデルをかぎりなく増殖させるのである。
「確かに、モオツァルトのかなしさは疾走する」(小林秀雄)のではなく「迷走するオブセッション(強迫観念)」。これらのランダムな拡散が、やがて平衡状態に達するときに、音楽はシステムとしての危機(クライシス)をむかえる。



