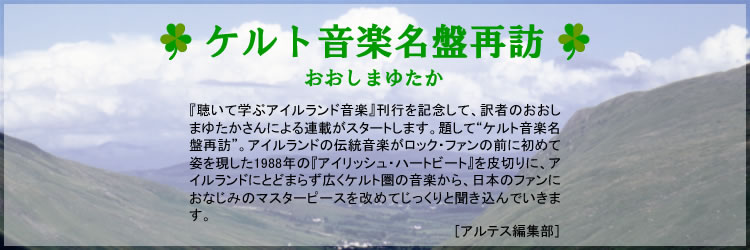
 【1】ヴァン・モリスン&チーフテンズ 《アイリッシュ・ハートビート》1988
【1】ヴァン・モリスン&チーフテンズ 《アイリッシュ・ハートビート》1988

このアルバムをリリースと同時におそるおそる聞いたとき、まず浮かんだのは、そんなに悪くないじゃないか、でした。不安のどん底での最悪の予想からはずっとマシなものに聞こえたのです。ジャケットでも、知名度において比較にならないほど大きなヴァン・モリスン一人が目立つこともありません。かれはロック・スターというよりは、むしろ、チーフテンズのメンバーの一人に見えます。まるで近所のオジサンたちという風情です。とはいうものの、諸手を挙げて傑作だと快哉を叫べるほどのものとも思えませんでした。
あまりにも耳タコの定番のうたをならべた選曲、リズム&ブルースやジャズをベースにしたヴァン・モリスンのシンギング・スタイル、それにベースやドラムスが入ったバックの編成。
こうした要素はそれまでアイリッシュ・ミュージックに多少とも親しんでいた耳には、ひどく場違いに響きました。他ではまず味わえない斬新な試みを喜ぶ心と、なじんだ暗黙の了解を踏みにじられたことを哀しみ怒る心が同居していました。
今ではこのアルバムは愛聴盤の一枚ですが、告白すればこの二律背反の想いはいまだに消えてはいません。聞きかえす度に、どこかおちつかない気分になります。ひょっとするとこのおちつかないところ、二律背反の想いを引きおこすところが、このアルバムの魅力の源泉かもしれません。
例えば〈ラグラン・ロード〉です。適切なテンポをとるのが、なかなか難しい曲です。それがどうでしょう。感興の赴くまま、詞の一節を繰り返すヴァン・モリスン。メロディを自由に展開して即興でうたうヴァン・モリスン。フレーズごとに発声を変えるヴァン・モリスン。思う存分うたいまくると「おうるらい」とバンドを促すヴァン・モリスン。
これはまさに絶好調のヴァン・モリスン以外の何ものでもありません。このうたは無数の人がうたっていますが、ここでのヴァン・モリスンの歌唱は文句なくベストです。
ところがアイリッシュ・ミュージックから見た場合、このヴァン・モリスンは、アイリッシュ・ミュージックの「掟」を残らず破っています。こんなうたい方はありえない、ぶち壊しだ、とアイリッシュ・ミュージック・ファンは頭を抱えてしまったのです。
ヴァン・モリスンはリズム&ブルースやジャズ、ソウルなど、ブラック・ミュージックを自分の伝統として身につけ、うたっています。その伝統ではうたい手がうたの化身となり、うたの感情をまといます。聞き手はうたい手が表にあらわす感情に共鳴します。聞き手が受けとる感情は、うたい手の表現するものに巻きこまれ統合されます。
アイリッシュ・ミュージックではうたい手はうたを通す筒です。アイリッシュ・ミュージックにとっての理想のうたい手は透明な声だけの存在です。うたの感情は聞き手の心の中に入ってから点火されます。聞き手の心の中にもともとある、共鳴する要素に火が点きます。聞き手が受けとる感情は、各自の内に秘められ、表に出ることはあまりありません。これに慣れた耳には、ヴァン・モリスンのうたはシンガーの存在が強烈すぎたのでした。
そこでアイリッシュ・ミュージック・ファンは、自分のなかの矛盾に悩むことになりました。これはいったい何だ。アイリッシュ・ミュージックか。ヴァン・モリスン・ミュージックか。こんなうたい方があっていいのか。こんなドラムスやベースがあっていいのか。こんなリズム処理はチーフテンズ本来のものでもなければ、アイリッシュ・ミュージックのものでもない。でも、このうたは、音楽は、すばらしいじゃないか。これをいったいどう聞けばいいのだ。
そういう矛盾をなんとか解けないかと、もう一度聞くことになります。一度や二度聞いたくらいで解ける矛盾ではありません。というよりも、聞くほどに矛盾はますます存在感を強くしてゆきます。ついには相反する気持を味わうこと自体が快く感じられる、そんな気にさえなります。ヴァン・モリスンのうたはそれほどにすばらしい。だからまた聞く。それを繰り返しているうちに、ある日、ふと気がつきます。
アイリッシュ・ミュージックのルール? 掟? そういうものはほんとうにあるのか。あるとしても、誰かが警察となって、違反者を取り締まってるわけじゃない。そうではなく、アイリッシュ・ミュージックのルールや掟は、それを担う人間一人ひとりが参加して決ってゆくものだ。ここに全身全霊でうたうシンガーがいて、そのうたが圧倒的な説得力で迫ってくる。アイリッシュ・ミュージックかどうかという前に、この音楽は最高だ。これをアイリッシュ・ミュージックと呼ぶ人がいるならば、それはそれでいいじゃないか。
こうして、このアルバムは、アイリッシュ・ミュージック・ファンが自ら閉じこもっていた蛸壷から、ファン自身を解放する役割も果たしたのでした。むしろ、アイリッシュ・ミュージック・ファンは、籠もっていた蛸壷がこのアルバムの衝撃で木端微塵にされたときに、初めて自分が蛸壷に籠もっていたことに気がついたのです。
こんにちこのアルバムはヴァン・モリスンにとってもチーフテンズにとっても傑作とされています。ヴァン・モリスンとチーフテンズの共演をあやしむ人もいません。けれども20年前の発表当時、チーフテンズのファンつまりアイリッシュ・ミュージックのファンがこの組合せに抱いた不安の大きさは、思いおこすだに異様なほどのものでした。両者を知るほどに、それぞれの音楽を愛するほどに、不安は大きくなりました。その二つが組んだ衝撃を何に喩えましょうか。マドンナがニューヨーク・フィルと共演してブロードウエイ・ミュージカルのスタンダードをうたう、というのはどうでしょう。いや、その方がまだ可能性は大きそうです。
いったいチーフテンズとヴァン・モリスンが一緒になって、何をやるのだ。ヴァン・モリスンはロック歌手だ。のはずだ。が、チーフテンズがチーフテンズである以上、フェアポート・コンヴェンションやムーヴィング・ハーツにはなりえない。ヴァン・モリスンがアイリッシュ・ミュージックをうたうのか。まさか〈アーサー・マクブライド〉なんかやってるんじゃないだろうな。確かにポール・ブレディを乗りこえられるシンガーがいるとすれば、ヴァン・モリスンしかいるまい。
それともチーフテンズが4ビートを刻み、ブルースを奏でるのか。想像しただけで世界が軋み、時空に亀裂が入るのが感じられる。
ヴァン・モリスンのファンにとって不安はなかったにしても、不審な想いは否定できなかったでしょう。このチーフテンズというのは何者だ。新しいバック・バンドか。しかし、ヴァンは自分のバック・バンドに名前をつけても、アルバム名義に入れたことはない。「&」は本来対等な関係を表す。ヴァンに対等な扱いを受けているのはなぜだ。
え、トラッド? アイリッシュ・ミュージック? なに、それ? そりゃ、ヴァンはアイルランド出身だけどさ。じゃ、チーフテンズというのもアイルランドのバンドなの? で、何やってるの? カントリーかい。ブルーグラスに近いものか。じゃあ、今回は純アコーティック・アルバムなのかな。〈アンプラグド〉がブームになるにはまだ早すぎるよ。ここんとこ、ヴァンもなんか調子悪いからなあ、そんな得体の知れない連中と組むとなると、ひょっとするとほんとうにヤキがまわっちまったのかねえ。
そう、ヴァン・モリスンがこれに先立つ時期に絶好調であったなら、このアルバムが生まれなかった可能性は小さくありません。ヴァン・モリスンはチーフテンズと組むことによって、シンガーとしての魂をつかみなおしました。これにつづく《アヴァロン・サンセット》以後の四部作に漲るエネルギーは、 80年代のヴァン・モリスンには望むべくもありません。
ではなぜ彼はチーフテンズと組んで、アイリッシュ・ミュージックに「起死回生」を賭けたのか。そこには、折から盛りあがるワールド・ミュージック、すなわちユッスー・ンドゥールやサリフ・ケイタに代表されるシンガーたちの台頭が底流となっていたにちがいないとする見方に、ぼくはこのアルバムを聞きかえすたびに、ふかくうなずきます。
そしてチーフテンズはこのアルバムによってブレイクしました。世間はチーフテンズの音楽がアイリッシュ・ミュージックだと信じました。実をいえば、このこともこのアルバムを聴く時の想いが複雑になる理由の一つです。なぜならチーフテンズがアイリッシュ・ミュージックのバンドだとしても、アイリッシュ・ミュージックはたった一つのバンドで代表できるような単純なものでも小さなものでもないからです。パディ・モローニはすべて自分の手柄のように言いたがりますが、それはアイルランド人独特のホラ吹きの現れでもあります。
ただ、このアルバムを企画した時のパディ・モローニが危機感に駆られていたことは確かです。1980年代のアイリッシュ・ミュージックは低迷していました。有力な新人も現れず、ベテランたちもどちらへむかえばよいのか、わからなくなっていました。経済の悪化でアメリカに移住するミュージシャンも相次ぎました。おかげで一時アメリカでアイリッシュ・ミュージックが大いに盛りあがったほどです。
チーフテンズ自身、行きづまってもいました。このアルバムを作る前に、チーフテンズは中国に行き、地元のミュージシャンたちも巻きこんで《IN CHINA》のアルバムを作っていますが、これも閉塞状態を打開しようとする試みの一つです。ヴァン・モリスンと組むことは、チーフテンズにとっても清水の舞台から飛びおりる覚悟が必要でした。ドラムスとベースの採用にあらわれているように、それまでのチーフテンズのスタイルを捨てることでもあったからです。身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ。チーフテンズはこの時、他の誰もがなしえなかったことをやってのけました。そして突破口を開いたのです。
ここにアイリッシュ・ミュージックをめぐる環境は一変しました。学生時代にはぼくがアイリッシュだ、スコティッシュだと騒ぐのを鼻で笑っていた友人が、このアルバムが出てしばらくして、「チーフテンズっていいねえ」とのたまわったものです。
そしてその変化に呼応するように、これを魁として、「ケルティック・タイガー」と呼ばれたアイルランドの経済成長をバックに、エンヤ、『リバーダンス』、映画『タイタニック』などのヒットを推進剤として、アイリッシュ・ミュージックは世界音楽の中に地歩を固めてゆくことになります。
アイリッシュ・ミュージックの内部においても、新しい動きは始まっていました。蓄えられたエネルギーが吹きだそうと蠢きはじめていました。そのひとつは北からの風でした。アイルランド北部のドニゴールは、それまで「忘れられた」地域でした。アイリッシュ・ミュージックの中心地の一つとされている今では信じられないかもしれませんが、これもまたこのアルバムから始まる変化の一つです。
そのドニゴール出身のフィドラー兼シンガー、マレード・ニ・ムィニーとベルファスト出身のフルーティスト、フランキィ・ケネディがプロとして出発したアルバム《アルタン》を発表するのは、このアルバムの前年。このアルバムをはさんだ2年後《ホース・ウイズ・ア・ハート》をリリースして、新たなバンド、アルタンは奇蹟の三段跳びへの助走を開始します。
 【2】アルタン《レッド・クロウ》1990
【2】アルタン《レッド・クロウ》1990

《レッド・クロウ》は衝撃でした。当時国内盤を出していたレコード会社の担当者から一足先に聞いてみてくれと送られてきたCDをかけはじめたとたん、椅子からとびあがりました。とてもじっとすわっていられなかったのです。
それまで聞いたこともない新鮮で、ダイナミックで、美しい音楽に、ただただ有頂天になりました。これは凄い、凄いよ、やったね、と最後まで聞きおわらないうちに担当者に電話をかけていました。新しい時代が始まった予感がありました。こういうものが出てきたのは、風が変わっている。いや、新しい風が吹きはじめたのだ。これはプランクシティでもボシィ・バンドでもない。チーフテンズとは対極だ。なにかまったく別のもの、オルタナ・アイリッシュ・ミュージックとでもいいたいもの。
およそ表現をなりわいとする者にとって、独自の「声」をつかむことは、まず何より大切なことではあります。やや極端に言えば、独自の声をつかめるまでは、表現者は「コピー」の域を脱することができません。
《レッド・クロウ》でアルタンは自分たちの声を掴みとったのです。その声で奏でられるみずみずしく、溌剌として躍動する音楽に、筆者ははじきとばされたのでした。アルバムの出来栄えということでは《アイランド・エンジェル》(1993)を頂点とし、《ハーヴェスト・ストーム》(1992)がこれに続くという意見に、筆者も同意します。しかし、声を掴んだ手応えに昂揚するバンドの反応は、《レッド・クロウ》に独得の輝きを与えています。例えていえば、わが国の代表チームがサッカー・ワールド・カップ本大会への初出場を決めた「ジョホールバル」の試合が持つ輝きに似ています。
アルタンの中心メンバーであるフランキィ・ケネディ& マレード・ニ・ムィニーは、1983年に《CEOL ADUAIDH(北の調べ)》を出してデビューしています。これは、ある人が「ラブラブな音楽」と評した通り、二人のパーソナルな音楽です。ジャケットの写真に象徴されるごとく、ここでは二人はおたがいに向けて演奏しています。だからこそそこに聞かれる音楽は新鮮であったわけですが、バンドとして外に向けて放たれたものではありません。
4年後のセカンド《アルタン》では姿勢は百八十度変わっています。ジャケットの写真で二人は外を向いています。ここではドニゴールの共同体の外のリスナーに音楽が放出されています。デビュー作がいわば「青春の記念」であったのに対し、セカンドははっきりと自分たちの伝統音楽演奏を世に問うていました。
デビュー作ではうたはすべてアイルランド語の無伴奏でした。セカンドでは伴奏を付け、アイルランド語と英語の詞を交互にうたうこともしています。このやり方はアイルランドの伝統にあるもので、「マカロニック」と呼ばれます。
そして何よりもドーナル・ラニィをプロデューサーに迎えたこと。プロデューサーとしてのかれの手法はミュージシャンの資質にできるかぎり添うものである一方、全体のベクトルとしては伝統音楽を伝統とは縁遠い現代人の耳にいかに魅力的に聞かせるかに腐心します。その点ではパディ・モローニと同じです。違うのはパディが音色の多彩さに傾くのに対し、ドーナルは楽曲にそなわるダイナミズムを引き立たせるところです。
ドーナルは例によってすぐれた手腕を発揮して、このアルバムを「外部」にとっても魅力的なものにしています。が、あくまでもフランキィとマレードの二人のアルバムとしてです。すでにメンバーはそろっているものの、まだ名づけられていないバンドの気配はごく薄い。
2年後の《ホース・ウィズ・ア・ハート》で、バンドとしてアルタンの名が掲げられました。これまでの4人のメンバーにポール・オショーネシィが加わり、ツイン・フィドルになります。プロデュースはフィル・カニンガム。スコットランドきってのピアノ・アコーディオンの名手。アコーディオンを持たせると常軌を逸する人ですが、プロデューサー、共演者としては出しゃばらず、ドーナル以上にミュージシャンの資質を尊重するタイプです。
《ホース・ウィズ・ア・ハート》は良いアルバムではありますが、アルタンの存在を明確に印象づけるまでにはいきませんでした。1980年代後半、アイリッシュ・ミュージックはようやく前半の低迷から脱出しようとしていました。アルタンのような新人が現れはじめ、ベテランたちも再び動きだしています。国外では「ワールド・ミュージック」ブームによって解き放たれた世界音楽が沸騰を続けていました。
そしてもう一つ。1989年から1990年にかけて、新譜のリリースがLPからCDへと一斉に切り替わりました。ある日を境に新譜がすべてCDになった。実際にはそんなことがあったはずはありませんが、そういう印象が残っています。アルタンにあっても《ホース・ウィズ・ア・ハート》は当初LPとしてリリースされた最後のアルバムです。
音楽界は騒然としていました。その中で注目されるには、良いだけではまだ足りません。この時期にあっては、むしろ1983年のデビュー作の鮮烈な印象が尾を引いていました。《レッド・クロウ》はそこに登場し、アルタンの音楽の独自性を強烈にうたいあげて、バンドとしてのアルタンの存在をあざやかに浮きあがらせたのでした。
バンドとしての出発に際してフィドルを加えたのは思いきった判断でした。マレード一人ではデュオとしてはともかくバンド・アンサンブルの中ではいささか弱い、ありていに言えば音量が不足。それを補強すると同時に、ドニゴールの楽器としてはまず何よりもフィドルであることを前面に出すことにもなりました。
フィドルが複数になる形はスコットランドからシェトランド、さらにはスカンディナヴィアに多いものです。ドニゴールはアイルランド北端に位置し、南の国内よりも、文化的にも社会的にもスコットランドとより強く深く結びついています。むしろ北海文化圏の南端がアイルランド島北部に食いこんでいる、と見たほうがよい。
おもしろいことに、多数重なってもフィドルの響きは太くなりません。ノルウェイの数十本のフィドルの重なりでも、その響きはどこまでもさわやかです。アルタンのアンサンブルも太くはなりません。この点が、同じユニゾンでもボシィ・バンドとは違うところです。ボシィ・バンドにあってユニゾンするのはフィドル、パイプ、フルートという、音色も音域も異なる楽器です。ユニゾンの「幅」が広いのです。太い筆の一筆描き。ボシィ・バンドのアンサンブルの時として暴走する野性はそこから生まれています。
ドニゴールにはジグ、リール、ホーンパイプなどとならんで、ハイランズ、ジャーマンズなど、独得の楽曲群があります。こうした楽曲はそれまで注目されたことはありませんでした。いや、その存在さえ、ドニゴール以外ではほとんど知られていませんでした。ボシィ・バンドもクラナドもドニゴールが音楽的故郷ですが、どちらもこうした独得のレパートリィを演奏することはありませんでした。
アルタンのおかげでわれわれのみならず、ドニゴール以外のアイルランド伝統音楽家たちも、あらためてドニゴール特有のレパートリィのおもしろさに目覚めます。今では、こうした楽曲群はコンテストでの定番の演奏曲目にまでなっているそうです。
初めて聞く、エキゾティックなチューンの、細くて濃い線によるユニゾン。暴走するおそれのない、均整のとれた音楽。アルタンの基本形はこうまとめられますが、レパートリィはマレード&フランキィのデビュー作からすでに出ていますし、バンドの形にしても《ホース》で基本はできています。では《レッド・クロウ》はどこが違うのか。
《ホース》までは楽器はそれぞれ独立して聞こえます。《ホース》では2本のフィドルは左右に分かれ、フルートが中央に位置しています。ギターとブズーキが全体を両側からはさみこむ。
《レッド・クロウ》ではフィドルが中央に並びます。フルートはそのすぐ脇についています。フロントでユニゾンを奏でる楽器がぐっと寄っているのです。独立して聞こえていた楽器同士を分けていた隙間がなくなりました。楽器の響きが重なり、個々の楽器が同じメロディを奏でるというよりも、ひとつのメロディを複数の楽器が分かち合う、真の意味での「合奏」になっています。それまでは一本ずつの線が別々に立っていたのが、ここでは集中して並んでいます。アルタン独自の声とは、この細く濃い線の集中だったのです。
アルタン自身の演奏やレパートリィが変わったのではありません。変わったのは録音としてどう聴いてもらうかのヴィジョンです。実際の変化はごくわずかです。離れていた楽器がくっついた、それだけの違いで、聴き手が受けとる音楽はがらりと変わってしまったのでした。蛹が蝶になるような、恒星が超新星になるような、モノクロがフル・カラーになるような、つまりおよそ次元が異なる音楽に、それはなっていたのでした。
ここは録音というメディアのおもしろさであり、また怖さです。ライヴでは良くも悪しくも、ミュージシャンの生地が否応なく現われます。録音ではごく一部の組立てを変えただけで、音楽の本質がまったく位相を変えるのです。
もっとも《レッド・クロウ》の組み立てはライヴでの演奏により近いものだったはずです。当時のライヴを見ることはできませんでしたが、来日時のステージと基本は変わっていないでしょう。この形によってユニゾン・パワーが全開された時、アルタンの録音は無敵になったのでした。以後、最新作にいたるまで、少くともインストゥルメンタルの録音に関するかぎり、組立ては変わっていません。
それだけではありません。この組立ては、ことユニゾンの扱いに関するかぎり、その後のアイリッシュ・ミュージックの録音の標準となってゆきます。その先には『リバーダンス』のあの集団によるユニゾン・タップがある、というのは我田引水でありましょう。ですが、アルタンによってユニゾンの持つ力を録音の上で解放する手法が開発された結果、今度はユニゾンの力そのものがあらためて注目されたことは、感じとれます。ダーヴィッシュをはじめ後に続くバンドは、ユニゾンをいかに効果的に際立たせるかをモチーフとしてアンサンブルを組み立てるようになります。
《レッド・クロウ》のプロデューサーはP・J・カーティス。次の《ハーヴェスト・ストーム》も同じです。前任者とちがって、カーティスの本業がミュージシャンではないことも、この組立ての変化には、ひょっとすると関わっていたかもしれません。《レッド・クロウ》と《ハーヴェスト・ストーム》で、 1990年と1992年の NAIRD (North American Independent Record Distributors) の最優秀レコード・プロデューサー賞を受賞しました。
《ハーヴェスト・ストーム》ではキアラン・トゥーリッシュが入ってトリプル・フィドルとなります。ケイリ・バンドを除いて、こんな編成はアイリッシュ・ミュージックでは空前で、おそらく絶後でしょう。そしてこんなスピードで演奏するケイリ・バンドはありません。《アイランド・エンジェル》でポール・オショーネシィが脱けると、ダーモット・バーンのアコーディオンとニール・マーティンのチェロを加えます。ユニゾン担当楽器の一層の重層化でした。
《ハーヴェスト・ストーム》はトリプル・フィドルの威力十分で、これはもう頂点だと確信したものでした。こんなものを作ってしまって、これからどうするのだろう。そんなことさえ、思うほどでした。この時にはフランキィの病が公になってもいました。ですから《アイランド・エンジェル》が現われたときには、心底脱帽したものです。アイルランドのどんなバンドでも、これをしのぐものはおろか、肩をならべられるものも作れまい。アルタンこそは No. 1。
そしてアルタンの「三段跳び」に引っぱられるように、アイリッシュ・ミュージックは爆発しました。アルタンの同世代、かれらよりさらに若い世代、そしてベテランが、まるで「せーの」でタイミングを合わせたように、いっせいに活発に活動しはじめたのです。シャロン・シャノンのデビュー作が 1991年。ダーヴィッシュとキーラとニーヴ・パースンズのデビュー作が1992年。ディアンタのデビューが1993年。1992年にはまた例えばマット・モロイ、ショーン・キーン、リアム・オ・フリンの3人が《THE FIRE AFLAME》を出しています。そしてアンディ・アーヴァイン&デイヴィ・スピラーンの《EAST WIND》も1992年です。
アルタンは時代の転換点に現われて、状況を一変させました。もとよりアルタンがすべて独力でなしとげたことではありません。ですが、アルタンが強力無比の触媒兼推進剤になったことは確かです。アイリッシュ・ミュージックの現代化がプランクシティ~ボシィ・バンドによって始まったとすれば、20年後それを一つの完成形に昇華したのがアルタンでした。あれからすでに20年。アルタンの「次」ははたしてどこかに現われているのでしょうか。
[著者プロフィール]
おおしまゆたか
ヨーロッパの伝統音楽を聞きあさることが身の丈に合っていると自認するアームチェア・トラヴェラー。一方でアイリッシュ・ミュージックについて空言を弄し、駄文を草することも大好き。めざすは晴聴雨読。アルテスから訳書『聴いて学ぶアイルランド』が刊行されたばかり。そのほか最近の訳書には『ラーマーヤナ』(ポプラ社)、『レオンとポテトチップ選手権』『驚異の発明家の形見函』(東京創元社)などがある。
blog→http://blog.livedoor.jp/yosoys/
mixi→http://mixi.jp/show_friend.pl?id=2952812