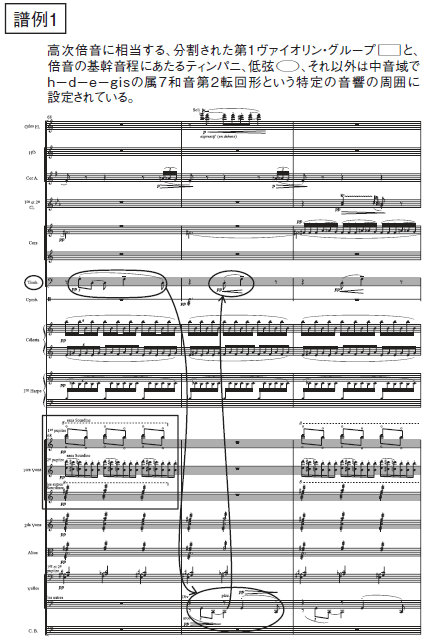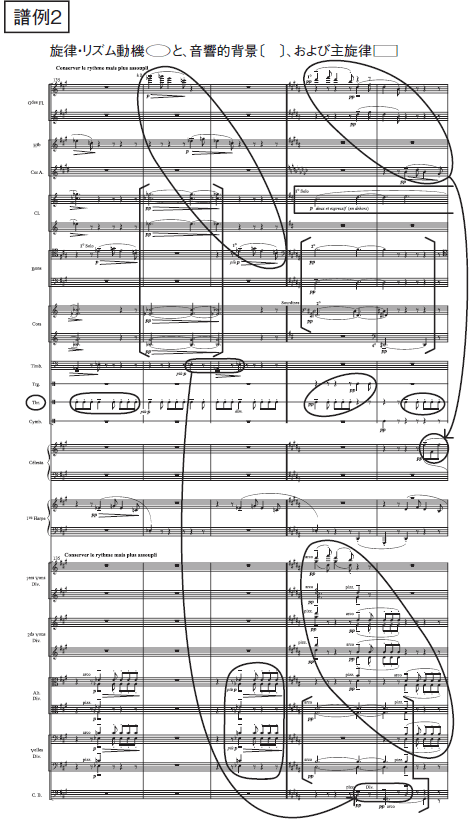音楽・知のメモリア (小鍛冶邦隆)
クロード・ドビュッシー(1862-1918)の音楽は、19世紀後半のロマン主義とフランス象徴主義の風土に開花し、いわゆる世紀末の芸術から20世紀初頭のベル・エポックの花咲く日々の思い出として、われわれの記憶に刻まれている。
さらに第一次世界大戦の前年、1913年に、ストラヴィンスキー《春の祭典》とともにロシア・バレエ団により初演された、オーケストラのための「舞踊詩」と題された《遊戯》や、戦時中の1915年に作曲されたピアノのための《12の練習曲》は、当初の否定的な評価にもかかわらず、第二次世界大戦後、シュトックハウゼンやブーレーズといった50年代の前衛作曲家たちによって、その新しい音楽思考の観点から再評価されたのは周知のことであろう。
ヨーロッパの旧世界を解体した2度の世界大戦をはさみ、その評価が相反する(異なる)とも考えられる、ドビュッシーの音楽を再考してみよう。
《選ばれた若者》
1902年の《ペレアスとメリザンド》初演により、ドビュッシーは作曲家としての社会的評価を確立させる。また私生活においても、銀行家夫人のエンマ・バルダックとの不倫、妻リリーの自殺未遂、そして離婚という世間的スキャンダルをへて、1905年にボワ・ドゥ・ブーローニュ街の高級住宅地に移り、エンマと同居を始め、一人娘(シュシュ)が誕生……と、彼が夢みた上流の生活と創作の日々を獲得する経緯は、評伝的事実にいささか収まりきらない意味をもつ。
貧しい勤労者の家庭であるドビュッシー一家は、クロード5歳のときに郊外からパリ市内に移り住む。ドビュッシーは歓楽街ピガールと下町のサン・ラザール駅界隈をなんどか移り住みながら、1872年以降12年間におよぶ、パリ音楽院での学習時代を過ごすのである。
苦労して手に入れた(3回の挑戦)ローマ大賞という、オペラ作曲家として約束された将来も、彼一流の反逆的ポーズに加え、生きるために上流社会の音楽サロンでパトロン漁りをしなければならなかった青年作曲家には、あまり役に立たなかったようだ。もっともワグネリズム一色のパリ音楽界にあって、ワーグナーにならって(après de Wagner)でなく、ワーグナーを超えた(après Wagner)オペラを夢みたドビュッシーは、パトロンのおかげの2度のバイロイト体験と、パリ音楽院で受けたオペラ的作曲法の徹底的な学習を下地にしつつ、象徴主義と世紀末ふうの雰囲気に満ちた《ペレアスとメリザンド》(1893-1902)を抒情劇として構想することで、あくまでも伝統的なグランド・オペラとの差別化をはかる。
虚無の工場
ドビュッシーは、エンマとの費用のかさむ生活を維持するため、次作オペラの構想を模索しつつ、管弦楽のための3つのエスキス《海》(1903-05)や、ピアノのための《映像第1集》(1905)以降の革新的な音楽語法を試みる。
ところで1906年以降、翌07年にいたる、創作上の不毛な時期が知られている。あたかも「虚無の工場(les usines du Néant)」(1906年4月18日の、ドビュッシーからデュランへの手紙)ともいえそうな沈滞感のなかで、創作は停滞する。
しかし革新的語法という新たな「投機」は、意外なところで試みられる。
豊穣なワグネリズムの記憶でもある、ドビュッシー初期の歌曲集《ボードレールの5つの詩》(1887-89)第3曲〈噴水〉の(ピアノ伴奏部分の)オーケストラ編曲は、あまり知られていない。ドビュッシーは、《海》や《映像第1集》で試みた、響きと時間(音色構造と形式)のより先鋭的な実験をここでおこなう。がんらいワーグナーに由来する、管弦楽編曲ふうピアニズムをもつこの歌曲のピアノ書法は、ここにおいて、さまざまな楽器の音色・音形(音高)・リズム(持続)・強度とアーテキュレーションによって、徹底的に解体されるのである。また複雑なフィギュア化による、音像の多様な変化・移動により、ほんらいの調性的支点が、より根源的なスペクトルに分解され、あたかも音響的な迷宮でもあるかの様相を示すのである。1907年2月24日にコンセール・コロンヌにより初演されたこの編曲は、否定的に評価されたのみならず、明らかにその場かぎりの機会的作品として無視されたのはとうぜんであろう(いまだ再評価されていない)。
そこにみる創作方法は、時代性を共有する、技術と様式による伝統的な制作術(musica poetica)としての作曲法に対して、20世紀全般の方向性として、個的で自律的な、「エクスペリメンタル(実験的=経験的)」な創造のあり方が対比される。
律動づけられた時間と色彩
1907年は、ふたたび創作の夏がおとずれる。
3曲からなる管弦楽のための《映像第3集》第3曲として知られる《春のロンド》の構想が確実に進展をみるのである。
「私はしだいに、音楽というものは、その本質からして、伝統的で厳格な形式のなかでくりひろげられるものではないと確信するにいたりました。音楽は律動づけられた時間と色彩なのです……」という、デュランにあてた1907年9月3日の手紙は《春のロンド》の進展を伝えると同時に、この作品の本質的に新しい意味を語っていると考えるべきであろう。
あまり議論の対象としてとりあげられたり、演奏されることも多いといえない、比較的短い作品《春のロンド》を具体的にみてみよう。
前出の手紙のなかでドビュッシーは、同作品における「非物質性」にもふれているが、おそらく特定の音色構造とその時間的持続が形成する音楽形式が、(力学的、機能的な)従来の調的和声にもとづく、伝統的形式による音楽展開と対比されていると思われる。以下音色構造と時間的持続の2点から《春のロンド》の図式を描いてみる。とりあえず伝統的といってよい、ロンド形式が浮かびあがる(図表参照)。
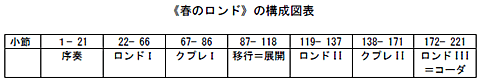
Images(映像)・現実と実存
管弦楽のための《映像第3集》(1905-12)は、《ジーグ》、《イベリア》、《春のロンド》の3曲からなり、ピアノのための《映像第1,2集》同様、各タイトルが暗示する描写的内容に反して、そこでは「現実(réalités)と異なるなにか」(ドビュッシー)、おそらく実存(réalité)が探求されている。images(映像=心象)を介して、現実界のとらえがたい変転そのものの背後に、本質的な現実=実存が眺望されるのである。
音響と時間の形式による新たな現実とは、現実の音響=ノイズと楽音、身体的リズムと音楽語法一般の韻律性の交わるところ、パルス(振動数)としての音高とリズム(音価)の相関性、そして調性的音響の倍音原理におけるスペクトルの試みとして探求される。
ところで身体的リズムとは、《映像第3集》のフォークロア的性格、《ジーグ》の英国、《イベリア》のスペイン(ハバネラなど)、《春のロンド》のフランス(《もう森へは行かない〔Nous n'iron pas au bois〕》と《眠れ、よい子〔Do,do,l'enfant do〕》といったフランス童謡が、5拍子の舞曲の主要主題として用いられる)の、特定のリズムパターンによる民謡ふう素材が、コンテクストを形成することを意味する。非ヨーロッパ文化圏への異国趣味とならんで、ヨーロッパ文化のファッション性は、今日の都市文化の原点としての国際都市、パリの同時代性(コンテンポラリー)の反映ともいえよう。
変ロ、変ホ、イ音という限定された音高を中心とする序奏(1-21小節)では、弦楽器のスル・ポンティチェッロ(駒の近くで)、スル・タスト(指板の近くで)という、通常の奏法に対して倍音の特徴的な制御と、字義どおり倍音を生成するハーモニックス奏法が集中的に用いられている。また同様にピッツィカートやトレモロも、音源アタック時の雑音やヴァイブレーションといった「変調(モデュレーション)」が問題となる。通常の楽音に対し、現実界の反映としての非楽音=ノイズが音楽的発想の原点となる。調的・和声的コンテクストに対し、音響的テクスチュアが対置され、新たな音楽構造・持続が試みられるのである。序奏部に現れる《眠れ、よい子》や、続いてロンドIにおける《もう森へは行かない》といった主題も、伝統的な主題性と異なり、たんなるテクスチュアの折り目に浮かびあがる音楽的瞬間を生み出すにすぎない。またほんらいのロンド主題と思われる第3の楽想(31小節以降)も、散在する一動機にすぎず、やがて音楽的展開のうちに散逸するのである(180小節以降)。
音楽的時間は、あたかも即興的な素材と形式のうちで、夢みるような持続として生み出される。
音響的スペクトルによる形式
1)クプレIの音響設定をみてみよう(68小節以降、譜例1参照)。
ここではスル・タストの弦楽器のトレモロとハーモニックス奏法により形成されるホ長調和音(実際には、イ長[短]調の属7和音e-gis-h-d)と、バスのオスティナート的なハ長調の複調的音響の摩擦が特徴化される。ティンパニの異例な高音をともなうg-cの張り詰めた音色感と、チェロのアルコ・ピッツィカートと分割された声部の形成する音色旋律としてのオスティナートの不変のバス進行が、調的推移とは異なる、音色的テクスチュアに聴覚を集中させる。そして高音域でソロ・グループとそれ以外に分割された第1ヴァイオリンや、他の弦楽器グループの生み出すトレモロやハーモニックスの、高次倍音に相当する動き(さらに木管楽器の微細な動機)が、細分化された振動数に相当し、中低音の倍音の基幹音程にあたる音程が、より緩やかな周期で反復されることで、音高(倍音)とリズム(音価)がパルス的に一致する、あたかも電子音楽的な発想がみられる。
シュトックハウゼンがドビュッシーの《遊戯》でおこなった分析は(『ウェーベルンからドビュッシーへ──統計的形式のためのノート〔1954〕)、とうぜんながら、50年代の具体音・電子音楽的発想を根拠とするものである。
2)さらにクプレIIへの移行とクプレII冒頭の音響設定を検討してみよう(135-139小節、譜例2参照)。
移行部(137小節まで)の中心的和音(音響)のas-c-es-gがクプレII(138小節以降)のgis-h-dis-fisと異名同音的変化により、音響的テクスチュアの変化が生ずる。単純な持続和音(長・短7和音)ではあっても、そこでは弦楽器群(補助的に木管楽器)の高音域から中音域への音像移動を、背後のハーモニックスを含む弦楽器と木管(ホルンを含む)の保続音響が、空間的に浮かび上がらせる。
また132小節以降、短く再現する第3の(主要)ロンド主題の最後の動機が用いられてはいても、(若き日のドビュッシーに強い印象を与えた)ガムラン音楽を思わすような、極小動機による一種のヘテロフォニーが意図されている、といってもよいかもしれない。
移行部におけるティンパニのリズムがコントラバスのピッツィカートに移り、いっぽうタンブラン(中太鼓)のリズムは不変であるところから、一定のリズムにともなう彩色法の変化が、律動づけられた音色としての局面を生成するのである。同様に、クラリネットに聴かれる、《もう森へは行かない》の拡大された旋律の彩色法でもある。
このように(2カ所のみの検証にすぎないが)各部分の固有の音色的テクスチュアが、コンテクストとしての形式を生み出す。《春のロンド》のみかけのロンド形式(類比による形成方法は《遊戯》と共通する)は、とうぜん伝統的形式としてではなく、音響的推移の形式としての音楽の対照、多様化という、聴覚上のフォーカス(焦点)を形成するにすぎない、といえばよいだろうか。
方法は異なるとはいえ、こうした管弦楽的音響にかんする新たな発想は、マーラー(第9交響曲第1楽章や《大地の歌》終楽章)を介して、1910年前後の新ウイーン楽派と共通項が認められる。シェーンベルク《管弦楽のための5つの小品》op.15第3曲〈色彩〉、ウェーベルンの《6つの管弦楽のための小品》op.6第4曲や、ベルクの《3つの管弦楽のための小品》op.6第1曲導入部などには、まさに楽音とノイズの音響的スペクトルがみられる。そして《春のロンド》の、1910年11月15日のニューヨーク初演をおこなったのが、マーラー自身であるのも象徴的といえようか。
同年3月2日に作曲者自身の指揮によりおこなわれた、パリ初演の後にみられる、用心深い批評に比べれば、「形式の崩壊」「痙攣的な」「混乱した響き」「常軌を逸したオーケストラの色彩」といったニューヨーク批評界の語調(H.-L.ド・ラ・グランジュによる引用)は、ドビュッシーの音楽というよりも、あたかもマーラーの後継者たちたる新ウイーン楽派の音楽を思わせる。
夢みるクロード
伝統的な音楽理解が、おおむね主題の提示・対比・発展・再現といった時間形式に支配されている事実は否定しようがない。しかしながら時間形式としての音楽を、聴き手はその時間を現実に所有することなしに、記憶と内的体験として、また時間的経過のプロセス(過程=手続き)全体として、把握するにすぎない。たとえば主題じたいがいかに正確に再現されようとも、一般的聴衆は、すでに提示された主題を正確に認知するのではなく、ありうべきプロセス=文化的慣習としてのみ、主題の再現を遡及的(形式的)に追認するのである。
近代における音楽の「形式」とは、その歴史的な根拠のあいまいさにもかかわらず、音楽聴取のテクノロジーの一部として、聴き手の音楽的理解の自由を「保障=担保(セキュリティ)」するものである。そして作者の名もこの「保障=保証」の一部となる。
しかしドビュッシーの音楽では、もろもろの音楽的契機(主題・リズム・響き・形式など)が、音楽的現実(実存)を生み出す瞬間を保証するのみといえる。時間=形式の彼方に、記憶と忘却、そして変容としての再生の刻を生み出す、作者の名も消失したところの自律的な記憶装置としての音楽的装置=配置(disipositif=disposition)が、ドビュッシーの夢みたものなのであろうか。
移ろいゆく魅惑の一刻を、永遠に留め置くためには、断続的に現前する音楽的瞬間を体験する快楽と、その喪失の空虚に堪えつづけなければならない。