音楽・知のメモリア (小鍛冶邦隆)
ヨハン・セバスティアン・バッハの《インヴェンション》《シンフォニア》と《フーガの技法》の音楽じたいに設定された、教育・理論的水準の一端を、前2回の連載でみた。
今回は《インヴェンション》《シンフォニア》がまとめられたと思われる1723年に先立ち、1722年ごろにはすでに成立していたと考えられる《平均律クラヴィーア曲集第1巻》から、よく知られているハ長調とハ短調の前奏曲とフーガを中心に、再度教育・理論的構想をみてみたい。同時に体系的な規範としてのコードが、読み解かれるべき暗号(信号)としても重要な意味を、テクストに内在させているところにも注目しよう。
隠された重複するテクスト
《平均律クラヴィーア曲集第1巻》の有名なハ長調の前奏曲は、《ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハのためのクラヴィーア小曲集》にみられる24小節の初期稿に各1小節計4カ所の部分的挿入と11小節の終結部分を追加するという規模の拡大のみならず、複雑なテクスト的再構成がおこなわれている。また初稿6小節以降は、右手3声、左手2声の和音配置のみ略記されている。とうぜんながら最初の5小節間で用いられているリュートふうの奏法(書法)にしたがって演奏できるのであるが、通奏低音法の実施例とも考えられるいっぽう、解読される体系(コード)を示しながら(初稿)、創造の段階的プロセス(改訂稿)を示唆するというバッハの教育・理論教育への基本姿勢がみられる。
ところで前者と調性的(同主短調)に対応する、鍵盤楽器特有のトッカータふうのハ短調の前奏曲(終結部分が初稿に対し11小節拡大された)は、おおむね右手3声、左手3声の和音の組み合わせが、ハ長調前奏曲同様に小節内で1~2つの和音を通奏低音の実施例として、音形化を要求される。さらに最初の9小節間はハ長調前奏曲(改訂稿)とほぼ同一の和声進行が用いられている。ハ長調前奏曲の9小節間には2カ所の新たな挿入(5、8小節)がおこなわれているだけに、結果的な音楽的テクストの重複の意味は大きい(譜例1参照)。
とうぜんながらバッハは、これらの対応する前奏曲に隠された重複するテクスト(同一の5~6声の和声進行)から、類型とそれらの差別化という課題を具体的に指示し、両者の異なる創作プロセスと演奏法のモデル(規範)を実施例として学習者に提示しているとも考えられよう。
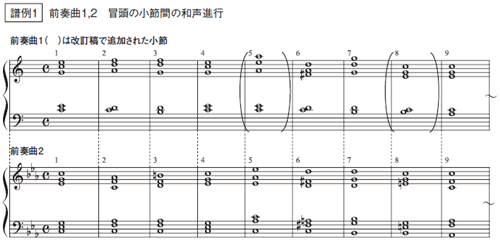
オシレーション(変動)・可変性(転回対位法)
前回にもふれたが、伝統的対位法の重要な技法である転回対位法は、対応する主題間(あるいは主題と対主題の間)で声部位置を上下に転回(交換)するさい、相互に対応する音程が変更され、音響的テクスチュアが変化する。《平均律》への導入過程と考えられる《インヴェンション》《シンフォニア》では、基本的な8度音程(1:2)の転回が用いられている。《平均律》の最初の2つのフーガでは、より複雑な12(=5)度音程(2:3)の転回が、〈フーガ1〉ハ長調の主題?対主題(2~3小節と6~7小節)で断片的に、〈フーガ2〉ハ短調の対応するエピソード間(5~6小節と17~18小節)でより厳密に用いられる(譜例2参照)。さらには〈フーガ4〉嬰ハ短調の終結部(107~108小節)では10(=3)度音程(4:5)が、伝統的な同時転回の技法(カノン・シネ・パウシス=先行・後続声部が同時に導入される、模倣間隔のないカノン)で導入されると考えられる。より高度な対位法技法の修得が《平均律》の課題の一部であることはまちがいない。
転回音程の変更は2つの声部(主題)間で交わされる、あたかも信号の変換のように、音程=振動数の変動により、音楽的素材の無限の多様化による消耗を回避しつつ、限定された素材の構造を可変的に多様化する方法を試みるのである。
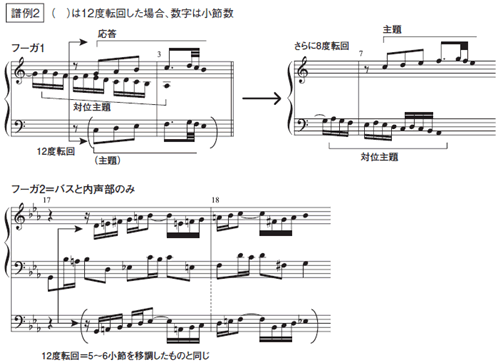
暗号数(コード)=14
よく知られているようにバッハは、自身の名前のアルファベットの数字への置き換え(BACH=2+1+3+8=14)による数14を、主題の音符数や、小節数、楽曲数に用いている。あきらかに意図的と考えられる例はそれほど多くはないが、〈フーガ1〉の主題の音符数は14であり、これは〈インヴェンション1〉の最初の主題の音符数を14にするための変奏を、自筆譜にわざわざ書き加えたことからも推測されるように、モニュメンタルな曲集を開始するにあたっての――b-a-c-hの音名によるものと同様――自身の署名であり、解読されるべき暗号(Sign=Code)でもある。
また〈フーガ1〉は、前半最後と後半最初の小節が共有(第14小節)されていることを前提に、それぞれ14小節からなっている。また〈フーガ2〉でも終結部分3小節以外、前半・後半14小節から構成されている。とうぜんながら小節数の一致のみならず、構造的に2部分性が主調・属調の対称性において成立するため、《インヴェンション》《シンフォニア》にみられる多部分性(おもに主調・下属調の対称性を枠組みに他の近親調を配する形式で、バッハのフーガ形式の一般的な特徴でもある)とはあきらかに異なるマニエラ(様式・仕様)がみられる。
主調・属調部分が相互に折り合わされた形式は、バロック組曲の舞曲形式や、のちのソナタ形式の初期の形態にしばしばみられるものであるが、バッハが《平均律第1巻》のフーガでしばしばそれらを用いているのは、バッハ自身の1720年前後の様式的な問題として理解できることなのであろうか。
音律と調律・TemperamentとTuning
《平均律》でバッハが用いた音律と調律法についてはさまざまな議論がある。
当時から知られていた5度圏循環の調領域によらず、ハ長調から同主調を組み合わせて半音階的にオクターヴを上行する方法は、《インヴェンション》と《シンフォニア》が全音階的に音階を上行する方法と対応する。
しかしながら、当時一般的であった純正3度を特徴とする中全音(ミーントーン)や、純正3度か純正5度を組み合わせたヴェルクマイスターなどによる調律法を前提に考えれば、同主調どうしの組み合わせでは、純正5、3度を5度圏に配分するさいの(シャープ系、フラット系の調の)相補性から、音律的な差異による音響的な特性化が生じやすいといえよう。
また用いられる調の内においても、音律・調律のひずみは、たとえば《平均律第1巻》の5声の〈フーガ4〉嬰ハ短調の主題におけるhis-eや、応答主題のfisis-hの減4度が、嬰ハ短調(あるいは応答主題の嬰ト短調)という音階音相互の不均衡な配列に対して、つねに純正(あるいは純正に近い)3度音c-e、g-hという異名同音として響くことで、ますます音響的な異質性を強調することから、音楽的テクスチュアが形成される。従来、象徴的に論じられてきた減4度の特性は、具体的な音律・調律的特徴から考察する必要がある。このように不安定な音響的条件のなかで主題は特化され、さらに主題を通じてテクスチュアとしての構造化が進行し、きわどい平衡状態が調的変化における時間的経緯として生み出されるといえよう。こうした聴覚と演奏する手・指という身体的にしか感知できない条件と、そこから時間の彼方に構造を予見する音楽的知の冒険は、すでに失われて久しいのである。



