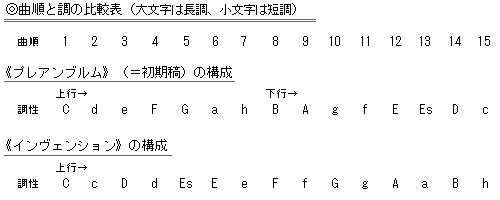音楽・知のメモリア (小鍛冶邦隆)
ヨハン・セバスティアン・バッハの《インヴェンション》と《シンフォニア》は、今日にいたるまでピアノ学習者の必須の教材として知られている。たしかにバッハ自身、この2つの曲集を1723年にまとめるにあたり、序文によく知られた教育意図──1)2声および3声のたくみな演奏技術、2)カンタービレの奏法の修得、3)作曲の予備知識を得ること──を明記したうえで、冒頭に「正しい指導(Aufrichtige Anleitung)」としるした。
演奏技術、芸術的趣味、作曲法といった音楽家に必要な職能を体系的に指導することは、バロック、古典派の作曲家にとって、創作活動と同等の重要性をもっていたと考えられる。そうした伝統において、教育活動に比較的距離をおいていたその後のモーツァルトやベートーヴェンが、より近代的(19世紀的)な音楽家として評価されている事実は興味ぶかく思える。
芸術作品? 教材?
ところでバロック、古典派期の専門教育(職業教育)における学習教材の目的は、演奏、作曲両面における伝統的技法と当世ふう趣味の修得と考えてよいだろう。バッハの《インヴェンション》と《シンフォニア》の各15曲は、多様な作曲技法と演奏技法修得への導入が意図されている。ルネサンス以来の伝統的対位法にくわえて当世ふうの和声的様式(通奏低音)という時代の共有財産を基準に、時代の要求する演奏・表現技法をモデル(範例)として学習できる作品集として構想されているのである。バッハにおいては、作曲家の創作が個人的価値をもつのは当然としても、さらに共有されるべき知識(savoir)としての継承=教育を意図する水準が、作品そのものに設定されていると考えてみる必要があるかもしれない。
秩序の再構築としての配列
分析・演繹可能な秩序の内部に特定の意味性を発見することは、バロック的世界観といえるが、そのひとつの過程を、バッハの作品集の配列にみることができる。その過程をここでみてみよう。
《インヴェンション》《シンフォニア》は、1720年以降の初期稿において、それぞれ《プレアンブルム》(前奏曲)、《ファンタジア》(広義の対位法的楽曲)とされ、長男フリーデマンの教育用作品集《ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハのためのクラヴィーア小曲集》に、異なった順序でおかれていた。ここでは《インヴェンション》についてみてみよう。
音階的にハ音からロ音にいたるまで上行する、白鍵で主和音が作れる7つの調(ロ短調のみ伝統的に一部半音的変化をうける)と、変ロ音からハ音まで下降する、前記以外の臨時記号をともなう主和音による8つの調による配列が《プレアンブルム》にみられる(「曲順と調の比較表」参照)。
全体的には4つの嬰記号、4つの変記号内の長短調のうちから、長調では音響的純度を最低限保てる4つの嬰記号、3つの変記号を網羅した調律法(ミーントーン)を前提に構成されていると考えられる(《平均律クラヴィーア曲集》にいたる調律=音律の問題については今後の連載でふれる)。
バッハは《ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハのためのクラヴィーア小曲集》から《インヴェンション》に再編成するにあたり、いくつかの重要な改訂をおこなっているが、各曲の音楽的水準には大きな変更はあたえてはいない。しかしながら個々の作品の配列を変化させることで、新たな秩序の発見、あるいは再組織化を継続する機能をあたえたとも考えられる。
新たな配列・配置=装置
バッハは《インヴェンション》で、同主調どうしのまとまり(ハ長調、ハ短調など)を前提に、ハ音からロ音にいたる上行のみの再配列をおこなった。とうぜん変ホ長調のように、対になる(6つの変記号が必要な)変ホ短調をもともと欠く場合も生じる。
しかしながら、この対になる音階音6音(ハ、二、ホ、へ、ト、イというヘクサコルド[伝統的ソルミゼーション])から生ずる計12の同主調と、それ以外の、組み合わせをもたない残り3つの調(変ホ、変ロ、ロ)を上行順に挿入する配列があらためて作り出される(「曲順と調の比較表」参照)。
この結果、同主調どうしの各曲の対応、また同主調の関係をもたない独立した3曲の特性、および両者のグループとしての関係が、結果的に《インヴェンション》における新たな順序も含めて複雑化する。15曲各曲が原則同一なのに対して、全体としての配列(Disposition)の変化から生まれる配置=装置(Dispositif)とは、なんであろうか。
対比をつうじて世界へ
《インヴェンション》第1曲と第2曲を比較してみよう。がんらい冒頭におかれていた第1曲にたいして、第2曲は初期稿では第15曲(終曲)であった。技法的にも第1曲の単純模倣に対し、第2曲の継続模倣(カノン)というように、前者の不断の創意(インヴェンツィオ)による自発的な発展に対し、後者のカノンによる2小節の先行楽句から対声部の模倣という後続楽句を創出する、自律的組織化による楽曲構成が対応する。とうぜんながらバッハの当初(初期稿)の学習プランとしては、音階的上行・下行という調的プランをつうじての、この発展的な対比が目的であったと思われる。しかしながら他の同主調どうしの組み合わせの基本原理にもみられるように、《インヴェンション》では(上行のみの調的プランとして)直線化されたにみえる構想も、そのコンテクストにおいて並列化することで、相互に入り組む螺旋的対構造に変化したともいえよう。
たとえば初期稿ほんらいのハ長調、ハ短調の始点と終点の回帰的関係が対比的=相補的に組み合わされることで、究極的な回路(音楽用語でいう連作[Zyklus])が設定され、15曲それぞれの構造(形式)を超越し、配列そのものが形式を生み出すべく起動する「ネットワーク」という世界認識の原理=装置が試みられるのである。こうした原理はバッハ後期の連作《フーガの技法》において、極限的に追究されるものといえよう。
さらに若干の例をあげるなら、《インヴェンション》第3、4曲(二長調、二短調)でコンチェルトと舞曲というバロック的器楽書法の対比、第6、7曲(ホ長調、ホ短調)における伝統的対位法的書法と当世ふうギャラント(和声的)様式、第10、11曲(ト長調、ト短調)における前奏ふう(即興的)技法と修辞的(衒学的)な技法の対比というふうに、初期稿から再配列されることで顕在化した新たな学習意図が指摘できよう。
《インヴェンション》では音楽的意味のみならず、内包する学習内容のプログラミングの変換の可能性においても、「作品」という水準が設定されるのである。
音楽という知、あるいは歴史的記憶(メモリア)としての音楽
音楽とは世界認識であるといった議論に、とりわけ郷愁をおぼえる必要はない。けっきょく音楽という行為じたいが、人間精神における知のあり方を代償的に再構成するともいえるのだから。
継承され不断に再構築される音楽は、つねに制度化されたあり方ともいえる。なぜなら音楽家の基盤はつねに社会的・文化的制度と不可分に位置づけられ、その変動は失われたものを伝統、変化したものを革新と称しつつ維持されるところからも推測できよう。
音楽における創作原理=作曲技法は、その表現原理である演奏技術とともに、巨大な歴史的記憶を構成する。その記憶=歴史(メモリア)は、伝承による音楽的ネットワークの修復と拡大を、制度として音楽家に要求しつづける。たとえそれらが、ヨーロッパ近代という局地的、時限的な制約をそなえていようと、人間精神の普遍的な原理を、特化された時代的パラダイム(範例)から、逆説的に明らかにするのである。