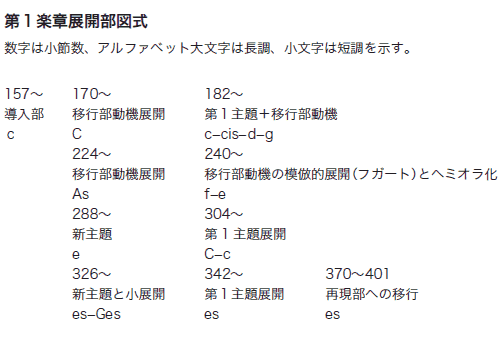音楽・知のメモリア (小鍛冶邦隆)
ルードヴィッヒ・ファン・ベートーヴェン(1770-1827)が1803年に完成した交響曲第3番《エロイカ》では、従来からさまざまなかたちで言及されてきた音楽の革新的な意味のみならず、作曲という行為の新たな水準が設定されたといえる。
《エロイカ》における、その異例なまでに拡大された形式と、特異な音楽的個性は、あたかも近代的芸術の誕生と同一視されてきたといってもよいだろう。
しかしながらそこで用いられている技術は、音楽的テクストを生み出す基準(18世紀的伝統における規範性[モデル])としてよりも、すでにパラダイム(規範)と化した「交響曲」という複雑なテクストを統御する技術(近代的テクノロジー)へと接近しているように思える。
18世紀以前の古典主義(いわゆる旧体制[アンシャン・レジーム])という前近代的システムに対し、フランス革命からナポレオン以降、19世紀初頭に出現する近代的システムが対峙するのである。
形式と統治
《エロイカ》第1楽章の拡大されたソナタ形式は、構成各部分の拡大のたんなる加算的な結果というよりは、現前するその広大な音楽的領土をいかに統一・統治するかという方法・複合的なテクノロジーの運用と、そのメカニズムの探求が課題となるのである。
三和音に単純化・記号化された第1主題に対して、多様な注釈・修辞が第1主題部から移行部へと地続きの領域を形成する。歌謡的な第2主題(83小節以降)、また第1主題と関連する小結尾(132小節以降)も、こうした多様なテクスチュアの構造のさなかに、象徴的・記号的意味として差別化されるにすぎない。ベートーヴェンの音楽について、しばしば語られるところの、主題とその発展にみる有機的統一とは、こうしたコンテクストより生ずるテクスチュアとして、音楽的素材を分類・配置する作曲法と考えるべきかもしれない。
近代的人間の象徴としての《エロイカ》主題は、提示されるやいなや、意識として内面化する(7小節以降)。再度主題が確認され(15小節以降)、発展する過程を「主題的技法(Thematik)」と言い換えることは可能だが、やはり「主題」じたいを対象化する作曲技法こそが、問題とされるべきであろう。
いうなれば、作曲技法としての主体性は、主題の側にはない。むしろテクスチュアとしての構造のなかに定位し、意図的に性格化された「主題」が、あからさまにまで対象化され、個別化されることで、統治=形式のネットワークが生み出される。
視点の在りか
第1楽章展開部は、その複雑で長大な規模により、《エロイカ》の巨大な相貌を象徴している。しかしながら展開部中央で出現する哀歌風の新主題(288小節以降)は、ホ短調という、主調=変ホ長調の遠隔調であり、また再度出現するさい(326小節以降)には変ホ短調という同主短調により、長大な展開部の折り返し地点として設定される(展開部図式参照)。
この新主題は、再現部に続く、展開部に比する長大なコーダ(これもこの作品の革新性とされる)にふたたび現れる(585小節以降)ことで、形式を生み出す諸関連性(有機性)のもとに組み込まれるかにみえる。しかしながら、むしろこの新主題(この楽章の主要主題からの乖離の度合いが重要であろう)を視点として、広大な形式的分布としてのテクストに一定の視野が設定されているとはいえないだろうか。
もちろん、この楽章におけるソナタ形式の扱いについて、(古典派にみる)伝統的モデル性というよりも、断片的主題性から構造化されるプロセス的発展という意味で、その革新性を強調するなら、その一過程(あるいは一時的な逸脱[エピソード])として新主題を理解することもできる。
しかしながら、これらの作曲法は、いっけん際限のない拡大にみえながらも、そこに一定の「規律」を生み出す内在的システムがあるように思える。作曲の規範(モデル)を生み出す(保証する)創作というよりも、創意のモデルとしてさまざまな個性の背後に、創造のメカニズムは身を潜めるのである。そして形式を一望のもとに見渡す、従来の分節点=主題や各部分の配分と異なる視点が、(意識する、しないにかかわらず)設定される。
暴力装置としての音楽
展開部における新主題出現にいたる経緯をみてみよう(展開部図式参照)。
移行部の動機による展開は、模倣的発展=フガート(240小節以降)から、動機的リズムのみを残し、第1主題部(25小節以降)にみられる、ヘミオラ化(254小節以降、3拍子2小節分が、2拍子3小節に聴こえる)に至り、(280小節以降)長7和音(転回形)=ナポリの6和音の変形から属短9和音(基本形)という、当時においても異例の不協和音を連続して用い、極点としての遠隔調=ホ短調の新主題を導入している。これらの不協和音は、身体感覚的な苦痛のみならず、ほとんど恐怖に近い感情を、当時の聴衆に与えたものと思われる。ここでは音楽的技法としての不協和音の歴史的な機能が、すでに形式を成立させるところの内面化した「規律」に対応すべく、懲罰ともいえる、もはや技法とは乖離した管弦楽的音響性の暴力へと変貌する瞬間である。そしてその直後の新主題の出現は、形式に潜む主体性(客体化)のまなざしであり、広大な展開部が一望される契機となる。
提示部同様に、移行部動機と第1主題部のヘミオラ・リズムによるテクスチュアから、第1主題音形が差別化される構図は、提示部の基本的テクストの転写・注釈となり、提示・発展という時系列としての伝統的形式は、新主題の出現によるパノラマ的展望(まなざし)を基点に、ネットワーク状の配置(disposition)、あるいは装置(disipositif)へと変わる。
身体性の意味、ふたたび
ベートーヴェンの音楽は、ある意味(本人も言明するように)、道徳的・倫理的といえよう。しかしながらそれらの「規律(discipline)」は、内面化(構造化)された身体性としてのみ体験可能ともいえる。ベートーヴェン後期様式に特徴的と考えられる、主題性の内面化(潜在化)としての構造性は、様式的発展の結果というよりも、むしろ諸関係のネットワークとして創造を実体化する手段として、「近代性」という装置の内部に遍在するものであろう。
またこれらの「規律」を起動させるものとして、音楽における身体性=素材のリズム的性格の強調、堆積、予測不能な変化・破綻といった手段が不可欠のものとなる。
《エロイカ》第1楽章が、主要楽章にまれな、どちらかといえば舞踊的な3拍子であり、さらに同終楽章の主題と一部の変奏が、バレエ音楽《プロメテウスの創造物》(1800-01)から流用されたことは偶然ではない(同様に同主題は《コントルダンス》[1802]の第7曲にも用いられている)。
第2楽章〈葬送行進曲〉も、第3楽章〈スケルツォ〉の小節構造の単位(4~8小節)で組織化された波状的運動性同様に、「行進曲」という象徴性のみならず、小節単位では極端に遅延化された拍動と、ほとんど痙攣的に細分化された装飾的リズム(冒頭のコントラバス音形のみならず、随所に聴かれよう)によって、やはり身体的に感知されるものといえる。
しかしながら問題としては、これらがベートーヴェンに特徴的な作曲様式として分類されることではなく、それらがいかに内面化(ベートーヴェンの聖化のキーワードでもある)され、いわば構造の側から、聴き手をどのように順化するかという聴取の制度化と、こうした作曲行為の主体性の在りかが問われなければならない。
同様に、いまだこうした「近代的人間主義」という視座のもとで、今日、作曲する意味を、自身と時代に問うてみるのである。